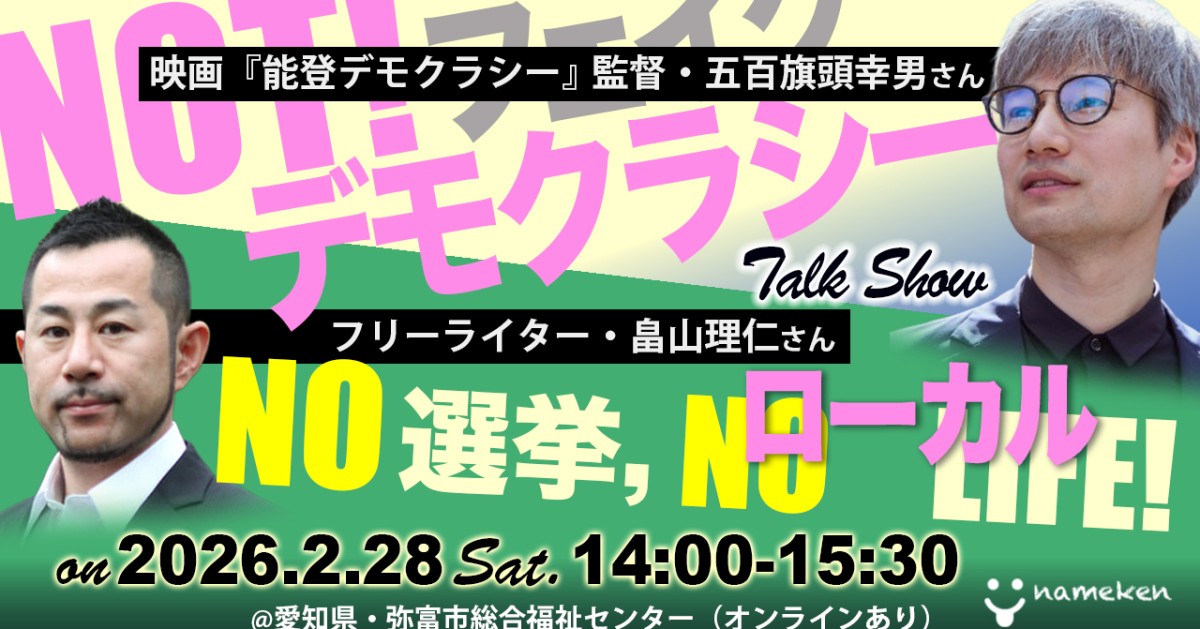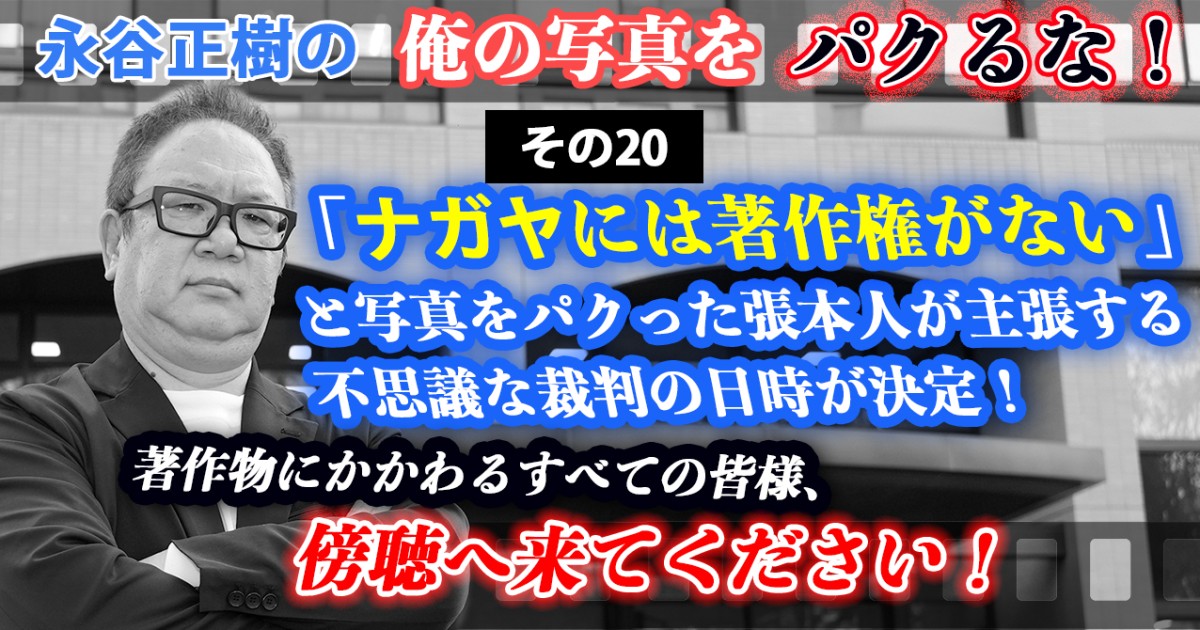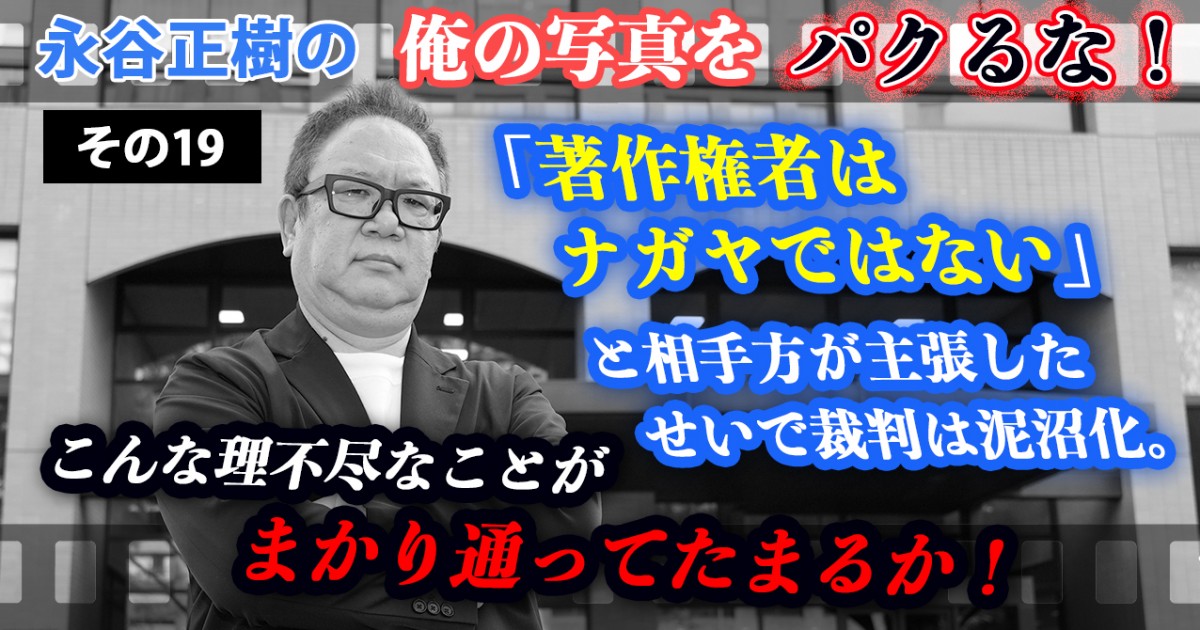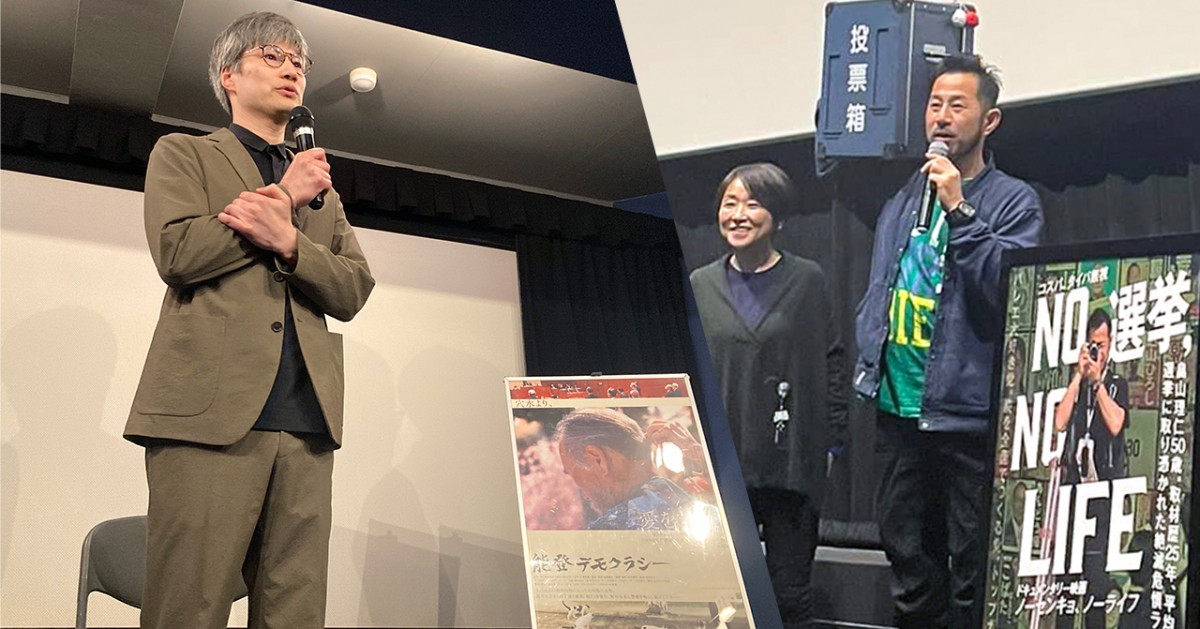関口威人の「フリー日和 (⌒∇⌒)□」その2・Twitterと僕の『ウェブ進化』
Twitterの動きから目が離せない1カ月でした。
先月27日にイーロン・マスクが買収を完了してから役員の解任、従業員の大量解雇、有料バッジの導入、そしてトランプらのアカウント復活…と本当に怒涛の展開。日本企業では考えられない決断とスピード感に「すげー」と驚きつつ、いちユーザーとしては使い勝手やセキュリティーがどう変わり、自分のアカウントがどうなるのか、やきもきするような毎日でした。
今ではイメージしてもらえないかもしれませんが、僕もTwitterはかなりのヘビーユーザーな時期がありました。
独立した翌年の2009年に「@sekiguchitaketo」のアカウントを作り、名古屋市政の動きや記者会見の開放などについて盛んにつぶやいてました。そして東日本大震災、特に福島の状況については現地の人たちや研究者の方々を含めて本当にいろんな議論をさせてもらい、学ぶことも多かったです。
でも、その反動というのか、2015年ごろには思いっきり「SNS疲れ」に。そこで気分転換に最初のアカウントを閉じ、「@newzdrive」の屋号にひっそり引き継いでみましたが、それも長続きはしませんでした。今も残ってる7年前のツイートは「NewsPics」のコメントと連動してみるなど、模索しておりました。まあNewsPicsさんもその後はアレになってきて…なかなか難しいもんだなあと思います。

僕の屋号「Newzdrive」名義のTwitterアカウント。ほとんどつぶやけないまま放置しちゃってます
遡れば、僕が初めてネットで発信したのは(メールを除けば)匿名のブログでした。
新聞社時代の2006年、知る人はよく知ってますが僕は3カ月間の育児休業を取りました。まだ男性の育休取得率が0.5%ぐらいだった時代。その理由は今回の本筋ではないし長くなるので、またいつかにします。とにかく、それまでいわゆる夜討ち朝駆けの社会部記者だった僕は、妻を働きに出した後、日中は生後9カ月の長男の育児と家事をワンオペでこなす逆転生活に入りました。
それは想像以上に大変で、毎日へとへとになりながら(妻から言わせると「まだ大したことないよ」でしたが)、夜は記録のためにとブログを書いていました。使っていたサービスは「FC2ブログ」で、今だとちょっとヤバいところかなと思うのですが、当時はサービスの数も限られていたし、育児系のブログが多かったので、見よう見まねで始めてみました。タイトルは「新米パパ記者の育休日記」なんてのに。もちろん今は全部削除してます。(ググっても出てこないのでちょっと安心しました)
「育休」中に偶然手にした一冊にのめり込む
そんなある日、散歩とネタ集めを兼ねて、ベビーカーを押して近所の書店に寄りました。そこで何気なく新書のコーナーで手にしたのが『ウェブ進化論』という本でした。最終的に40万部近くのベストセラーになったので、ご記憶の方も多いかもしれません。でも、僕が手にしたのは初版の奥付の発行日より前で、本当にたまたま書店に並び始めたばかりのタイミングだったようです。