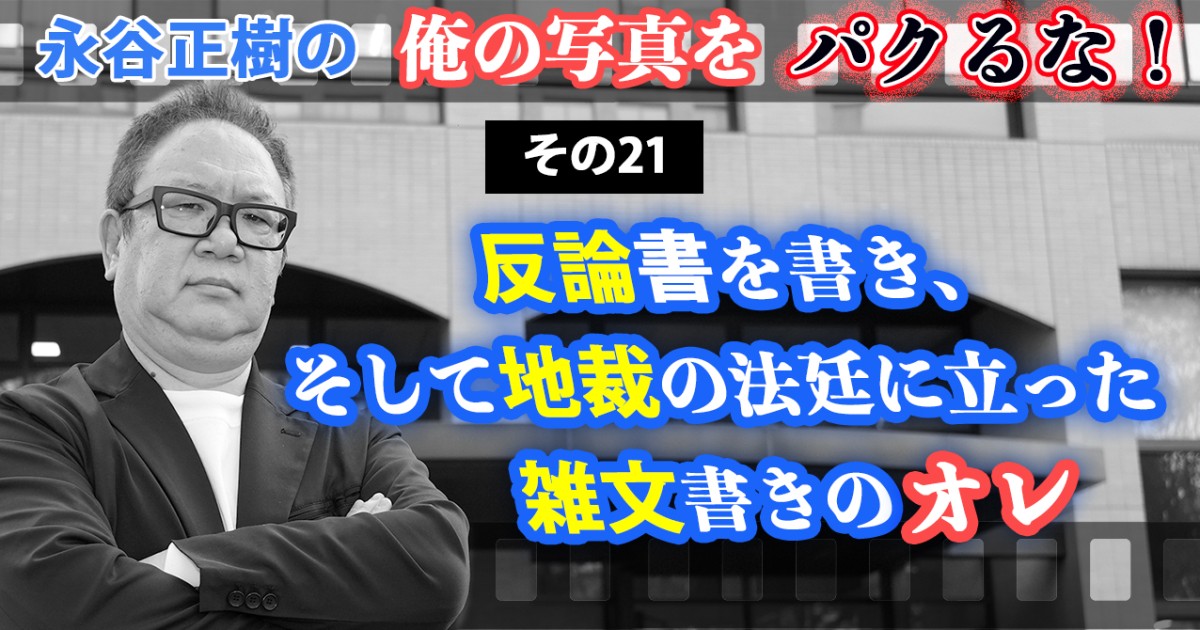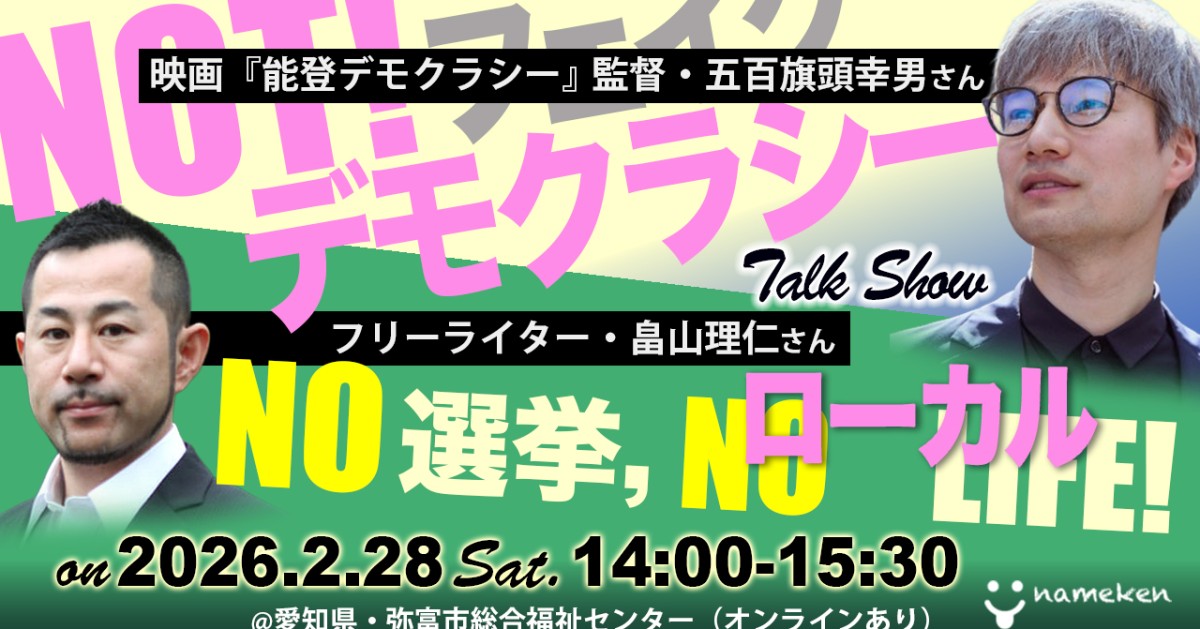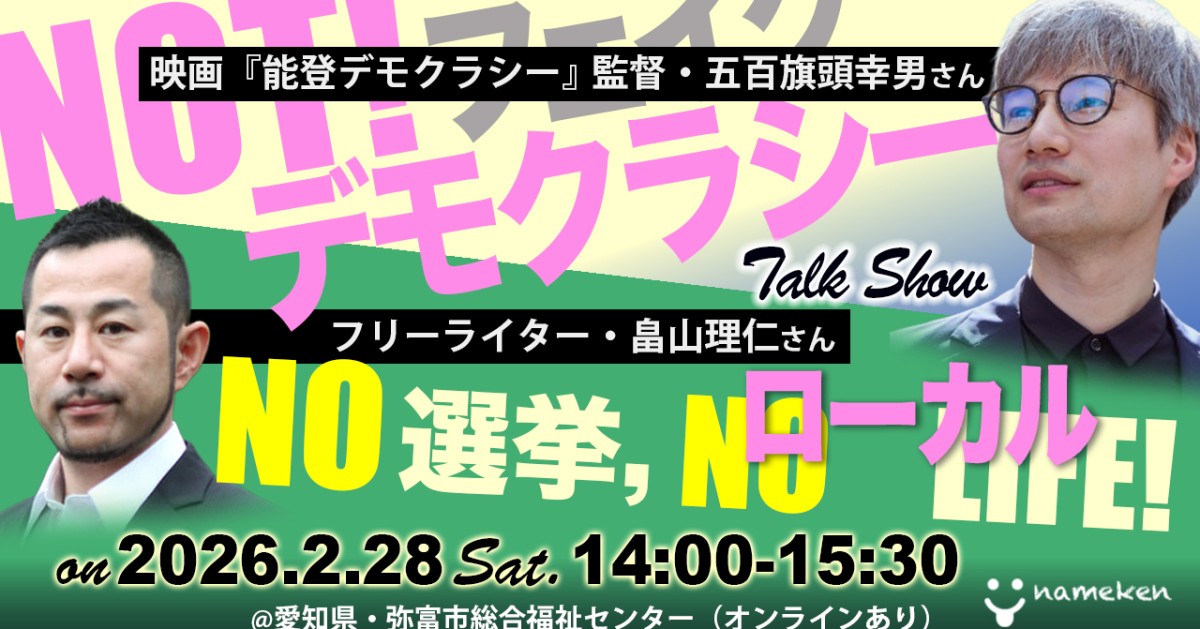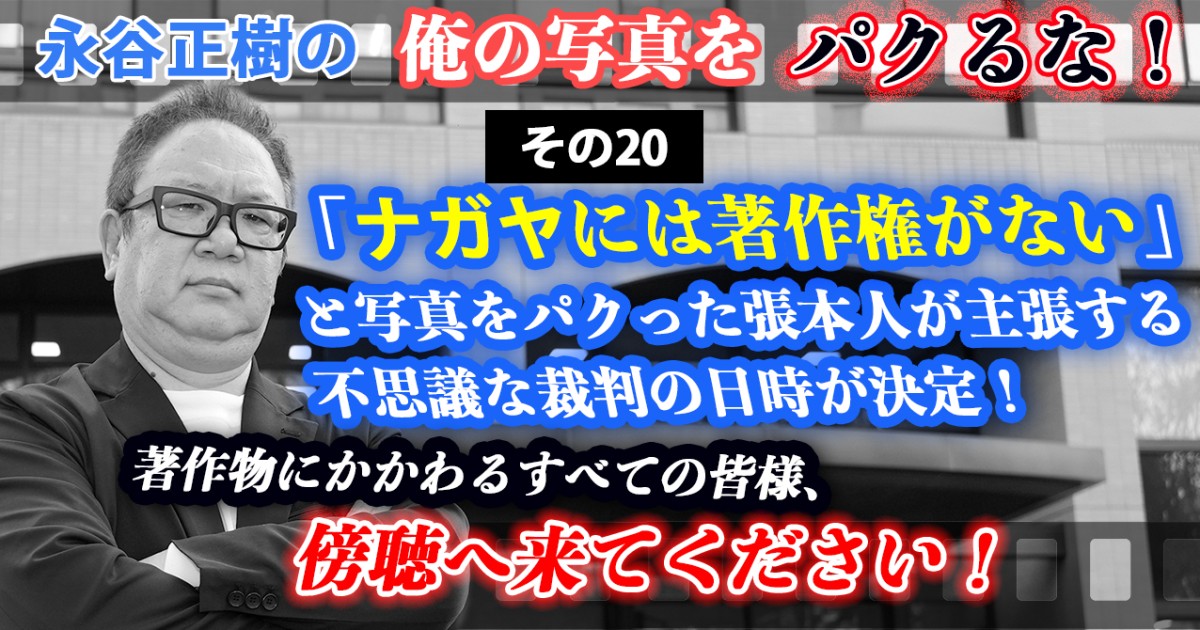三重県四日市市の水害、今と25年前【関口威人の災害取材ノート】
9月12日夜、発達した前線の影響で三重県北部などが大雨に見舞われ、四日市市では1時間に123.5ミリという観測史上最大の雨量を記録しました。
その前日、僕は名古屋で2000年の「東海豪雨」を語り継ぐ集いを取材して、当時の様子をあらためて思い返していました。
実は、25年前の僕は中日新聞の四日市支局に赴任したばかりで、名古屋に先立つ大雨を四日市で経験していたのです。
だから今回、そのときを凌ぐ雨の量だと知って、メディアでは地下駐車場の被害がクローズアップされているけれど、それでは済まないのではないか、「都市型災害」の中で埋もれる被害があるのではないかとやきもきしていました。
本当はすぐ現地に駆け付けるべきだったかもしれませんが、もろもろ調整してちょうど1週間となる19日(金)、名古屋から電車で四日市に向かい、現地を歩きました。
そこで分かった、極めて局地的ではあるけれど被害を受けた住宅地の様子と、地方記者時代の苦い思い出も残る現場を25年ぶりに再訪した様子をまとめてみます。
再整備が進む駅前の地下駐車場
僕は四日市市と菰野町に合計3年半暮らし、2004年に名古屋に移り住みました。しかし、その後もなんだかんだと数年に1回ぐらいは四日市を訪れていました。
でも今回、近鉄四日市駅を降りて驚いたのは、駅前での工事の多さでした。

再整備の進む近鉄四日市駅前。中央の近鉄百貨店に向かって左手に円形デッキ、右手にバスターミナルを整備するための工事が行われており、地下にある駐車場(くすの木パーキング)の冠水との関係も取り沙汰されている=9月19日、筆者撮影
駅前を再整備していることは知っていましたが、実際にリング状の空中歩道が姿を見せ、中央通りの車線が変更されているところまでは知りませんでした。この空中歩道(円形デッキ)は今年12月までには完成し、中央通りの半分をバスターミナル化する「バスタ四日市」は2027年春には開業するそうです。
今回、この再整備工事で出来ていた「穴」から地下駐車場へ水が流れ込んでいたことを、市当局自らが言及しています(9月16日の四日市市議会総務常任委員会)。ただ、そもそも駐車場側の止水板が故障していたという話があり、なにより時間120ミリという雨量が圧倒的で、その因果関係は簡単には分からないでしょう。
まずは被害にあった車両の所有者の特定や引き上げ作業など、やるべきことが山ほどありそうです。この日も駐車場運営会社(ディア四日市)の関係者や復旧の作業員が慌ただしく現場を走り回っていました。一方、今後の大雨時の対策などについては国交省を交えた有識者委員会で検討するそうで、全国的にも同様の地下駐車場を持つ都市が教訓にするべき事態だと思わされました。

今回の大雨で270台以上の車両が被害を受けた四日市駅前の地下駐車場「くすの木パーキング」。商店街のアーケード下などにある出入り口は一般の立ち入りが禁止されていた=9月19日、筆者撮影
住宅街の “静けさ” に違和感
ところで今回は、この地下駐車場被害のインパクトが強かったのか、周辺の住宅地の様子がなかなか伝わってきませんでした。ちょうど大雨が金曜の夜で、翌日から3連休に入ってしまったこともあるでしょう。行政も動きや発信が鈍かったと言わざるを得ず、住宅の被害数が公になったのは連休明けに開かれた上記の市議会委員会の席。僕はその日の夜に情報を聞きつけてYouTubeの録画で委員会での市当局の発言を確認したところ、「床上浸水200軒、床下浸水3100軒」という数字が出てきました。
しかも、これらは通報の多かった「中部、ときわ、日永」という3地区に限った数字だそうで、実際はさらに多いとみられます。最近の水害と比較すると、例えば甚大な被害がまだ記憶に新しい2018年の西日本豪雨で、ダムを緊急放流した愛媛県全体で床上浸水187(棟)という数字でした。人口密度が違うとはいえ、床上200という数字は決して少なくないどころか多い方です。にもかかわらず、この “静けさ” は何なんだろうという気がしていました。