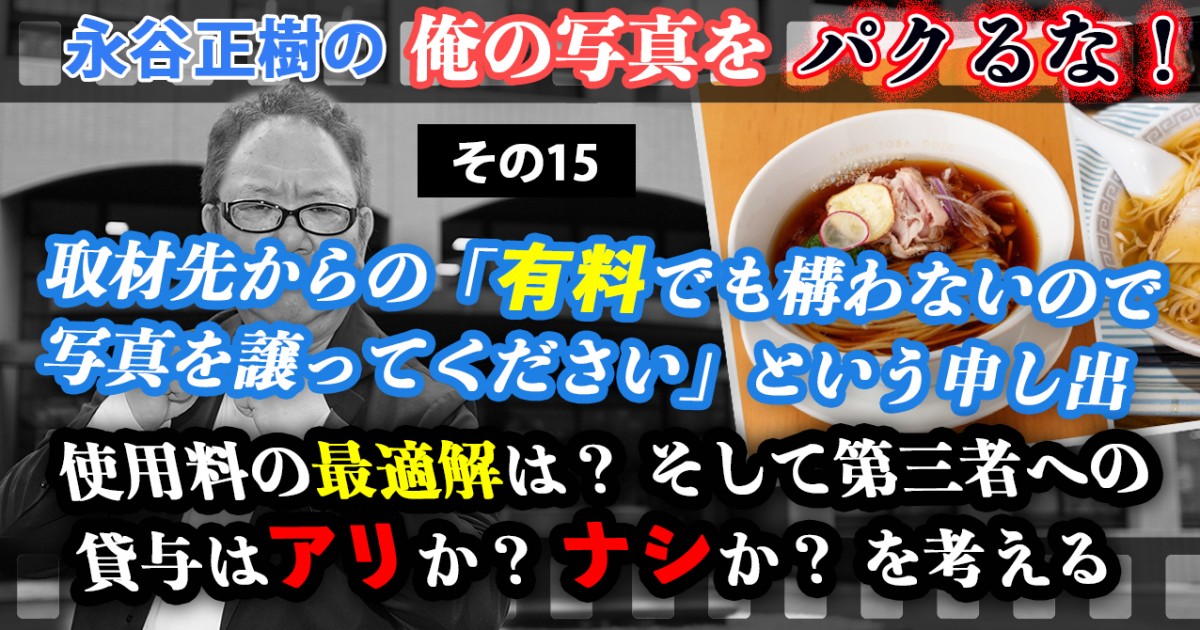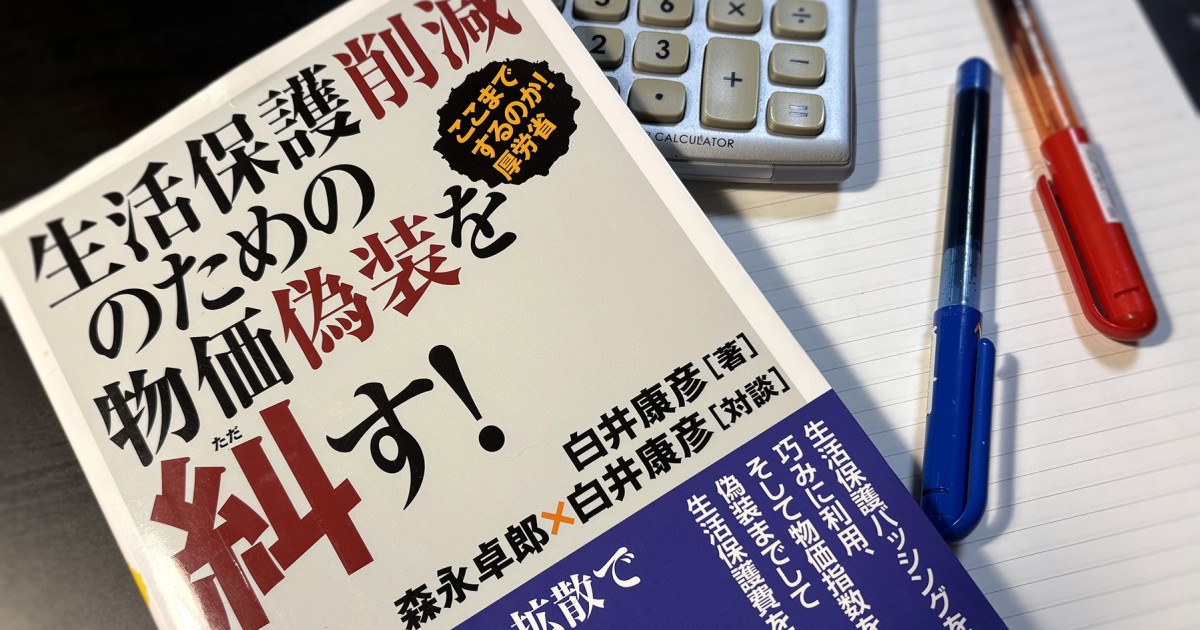永谷正樹の「俺の写真をパクるな!」その3・メディアと交わす契約書に注意せよ

紙媒体からwebメディアへと主戦場が替わり、仕事をする前に契約書を交わすことが当たり前になった。本来、契約書は双方の役割を明確にして、お互いの権利を守るためにあるのが理想だが、決してそうとは限らない。ライターやカメラマンにとって不利な条件を平気で書き並べるメディア運営会社もある。
カメラマンやライターと編集者の関係
私が写真専門学校を経て最初に就職したのは、主に会社案内やパンフレット、カタログなどを広告制作する会社だった。私が入社する前はデザインやコピー、写真などの制作は外部委託していたが、内製化することで利益率を高めようと思ったのだろう。同期にデザイナーやコピーライターもいた。
彼らは他の会社である程度のキャリアを積んでいて即戦力として重宝されていた。新卒採用の私は肩身の狭い思いをしていた。専門学校で身につけたスキルでは現場でまったく通用しないのだ。撮影の技術を教わる先輩もいないため、本を読んだり、実際に機材を設営してテスト撮影を繰り返したりするしかなかった。
それでもクライアントにとってはプロであるわけで、自信のなさをさとられまいと震える身体を気合で止めて笑顔でシャッターを切っていた。2年、3年と続けていると、それなりに技術が身についたが、私の心が晴れることはなかった。
なぜなら、広告の仕事はクライアントが絶対的な力を持っていて、黒いものでもクライアントが白といえば白になってしまうのである。私が渾身の力を込めて撮影した写真がボツになり、念のために「おさえ」で撮影した写真が採用されるのは日常茶飯事だった。そんな広告業界に嫌気が差して3年で会社を辞めて、編集プロダクションに転職した。23歳だった。そこから現在に至るまで30年以上メディアの仕事をしている。
25歳半ばで編集プロダクションを辞めてフリーとなり、これまで数多くの編集者との出会いがあった。編集者はカメラマンやライターに仕事を与えてくれる存在であるが、広告業界のクライアントのようなピラミッドの頂点に君臨しているわけではない。
30代前半の頃、一緒に仕事をしていた編集者に
「ナガヤに仕事をくれてやっているって思ってます?」と尋ねたことがあった。
「なんで?一緒に雑誌を作っている仲間じゃないですか」とその編集者は言った。
カメラマンやライターと編集者の関係は、野球のピッチャーとキャッチャーに例えられる。つまり、編集者は女房役なのである。その関係が私はたまらなく好きであるがゆえに、ここまで長く続けることができたのである。
あ、出版業界においても広告主であるクライアントは絶対的な力を持っているのは間違いないだろうが、現場で働く私がパブリシティ以外でクライアントの意向を意識して記事を書いたことは一度もない。
地元超優良企業が運営するwebメディアからのオファー
フリーになってこだわったのは、東京に編集部がある全国誌で仕事をすることだった。そもそも地元メディアに知り合いはいなかったし、どうすれば仕事がもらえるのかもわからなかったので、これまで積極的に営業活動をしてこなかった。
が、地元メディアからオファーをいただくことがあったら、引き受けようとは思っていた。そんなスタンスゆえに、地元メディアの制作に携わっている人からすれば、きっと私は生意気に映るだろうと思う。まぁ、どうでもいいんだけど。
2年前、地元の超優良企業が運営するwebメディアから仕事のオファーをいただいた。いや、正確に言えば、超優良企業からwebメディアの運営を委託された制作会社のディレクターからメールが届いたのだ。