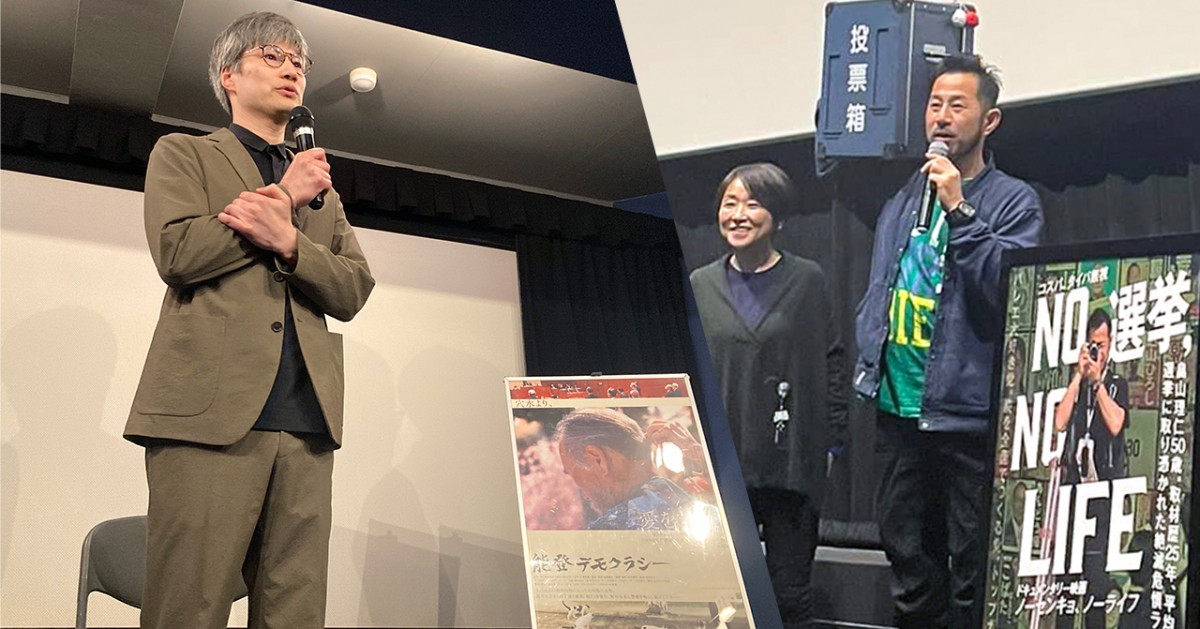永谷正樹の「俺の写真をパクるな!」その14・ふるさと納税サイト掲載窓口である自治体の怠慢とフリーランス法の施行に思うこと

まずは、製麺会社による写真無断使用の件。弁護士もサジを投げかけて、私も裁判でケリをつけようと思っていた。それがGW前のこと。その後、本当に粘り強く交渉してくださっている。
製麺会社は「やってない」との一点張りゆえに、外堀を埋めるべく、ふるさと納税サイトの運営会社と、サイト掲載の申し込み窓口となっている自治体に何度も問い合わせてくれた。根負けして、応じてくれたのはサイト運営会社。
写真のチェックを怠った自治体担当部署が隠蔽?
ただ、この案件は自治体が対応すべきと考えていて、そのスタンスは変わっていない。そりゃそうだ。本来であれば、製麺会社が用意した写真をチェックするのも窓口である自治体の役割なのである。それを怠ったため、私の写真が無断で使われたのだ。ある意味、運営会社も被害者なのかもしれない。
それでも運営会社は自治体に対してきちんと対応するように、つまり、弁護士に連絡をして事情を説明するようにと何度も要請したという。自治体の担当者は首を縦に振ったそうだが、現時点で弁護士には何の連絡もない。
「自治体は担当部署でこの件を抱え込んでいて、市の問題として他の部署や市長と共有していないのかもしれません。こちらが諦めるのを待っているのでしょう」と、弁護士は推測している。
何じゃそりゃ。それが本当なら、担当部署ぐるみによる隠蔽工作ではないのか。ヘタすりゃ自治体に対して責任を問われかねない。私ゃそんなケチなマネはしないけど。いちばん悪いのは、写真をパクった製麺会社なのだから。素直にやらかしたことを認めれば、こんなオオゴトにならずに済んだのに。企業としての信頼も失うと思う。ひょっとしたら、ふるさと納税サイトに出入り禁止になるかもしれない。まぁ、仕方がないだろう。
運営会社もこのままでは埒が明かないため、運営会社の社長の名前で自治体の担当部署ではなく、市長宛てに手紙を送るという。それを機に何かしらのアクションが起こると思う。っていうか、逆に何も起こらなければオカシイ。市長も隠蔽工作に加担したと疑われても仕方がない。仮にそうなったら、「なメ研」精鋭のジャーナリストである川柳さんや関口さんに闇を暴いてもらおう。
フリーランス法で変わった出版社の商習慣
さて、今回書こうと思うのは、発注書の話。昨年11月1日にフリーランス・事業者間取引適正化等法、通称「フリーランス法」が施行されたのは、皆様もご存知だと思う。フリーランス法は、企業などの発注事業者とフリーランス(特定受託事業者)との間の取引を対象として、契約内容の明示や報酬支払期日の設定、不当な経済上の利益の提供要請の禁止、ハラスメント対策など、様々な義務を発注事業者に課している。また、フリーランスの就業環境の整備として、妊娠、出産、育児、介護との両立への配慮や、ハラスメント対策に係る体制整備なども義務付けている。
フリーランスと事業者間の「取引適正化」を目的としているならば、いや、それ以前にギャラの値上げをしてほしいと考えるのは私だけではあるまい。まぁ、それは目を瞑るとして、このフリーランス法で大きく変わったと思ったのが、出版社からの仕事の発注スタイル。
以前は、担当編集から電話やメールで仕事の内容と〆切を伝えられてオシマイ。それを出版業界以外の人に話すと皆、驚く。
「えっ? 口約束? お金の話もしないの !?」と。
webメディアの場合は、あらかじめギャラを提示され、発注書も送られてくる。新規で仕事を受注する場合は契約書も交わす。しかし、雑誌はというと、発売した後にギャラが振り込まれてから初めてギャラの金額を知ることになる。
「えーっ! あんなに頑張ったのに、たったこれだけ !?」と不満に思うこともある。その逆で「ありがとうございます! 一生ついていきます!」と思わず小躍りしたくなることも。
この商習慣は私がフリーランスとなった30年前からずーっと続いていたし、こちらからギャラの金額を尋ねるのも何となく抵抗もあったから、それが当たり前だと思っていた。
ところが、先日、某出版社が発行する週刊誌の仕事のオファーをいただいたとき、メールに「発注書」が添付されていた。そこには、委託内容と委託料(ギャラ)、納品期日(〆切)、支払期日がきちんと記されていた。担当編集から
「公取(公正取引委員会)からの指導があって、これから発注書を送らせていただくことになりました」との説明もあった。