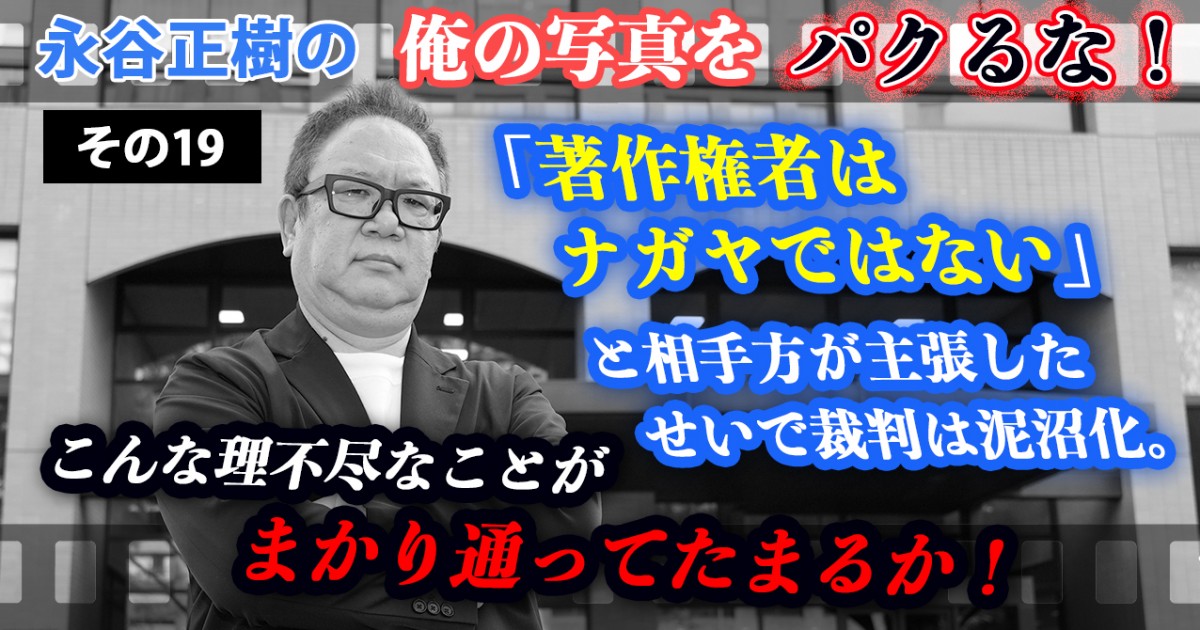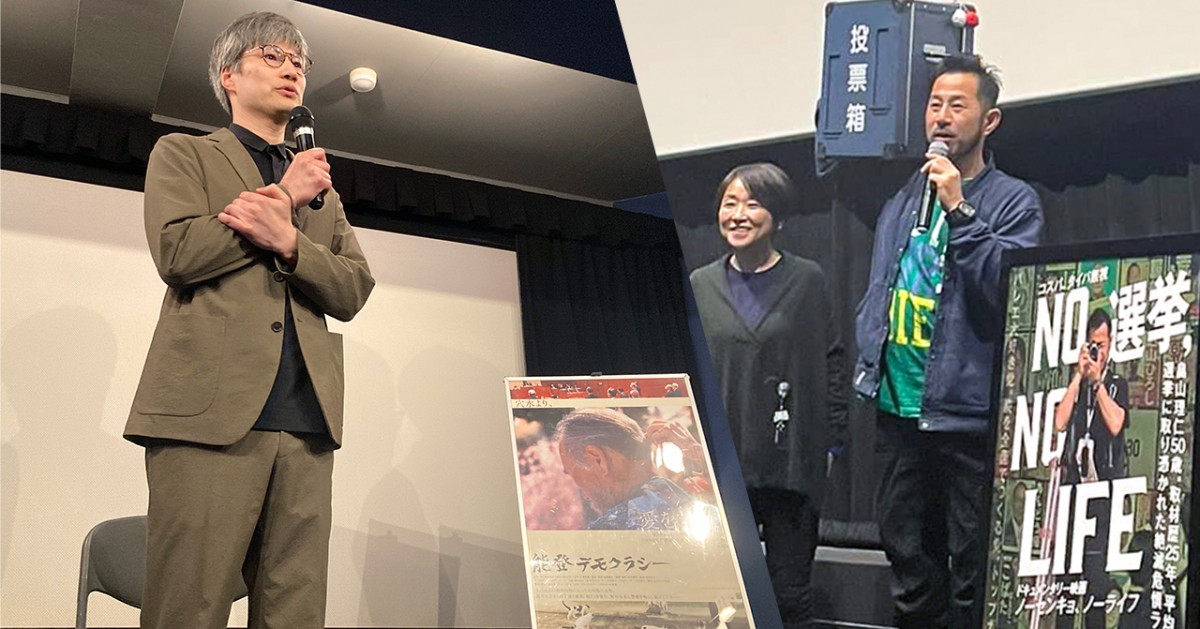私は何を“生成”しているのか?・石黒好美の「3冊で読む名古屋」⑫
【今月の3冊】
『創るためのAI 機械と創造性のはてしない物語』(徳井直生、ビー・エヌ・エヌ)
『霧のコミューン』(今福龍太、みすず書房)
『デジタルで読む脳 × 紙の本で読む脳』(メアリアン・ウルフ 大田直子訳、インターシフト)

最近は以前ほどGoogle検索を使わなくなりました。確定申告のやり方からちょっとした翻訳、冷蔵庫で古くなりつつある大根とベーコンを使ったレシピまで、ChatGPTに聞いた方が早いからです。
プログラミングの知識もグラフィックデザインの技術もなくても、たちまちプレゼン資料もイラストも動画も出来上がる――アイデアはあるけれどアウトプットのスキルがなかったり、あるいは手を動かす時間がなかったりという人にとっては、生成AIは夢のようなツールだと思ってしまいます。
一方では「AIに仕事を奪われる」といった不安や懸念の声も根強いものです。そう言われればいま生成AIに興味を持って積極的に使っている人は「AIでもできそうな仕事」「AIに代替されそうな仕事」をしている人ではないでしょうか。いかにAIを上手く使いこなすかと奮闘しているのはホワイトカラーの人ばかり。老人ホームでおむつを替えたり、ゴミの収集をしたり、お米や野菜を育てる仕事をAIがやってくれる日はまだ遠そうです。「なメ研」でも今のところあまりAIの話題にならないけれど、被災地で何が起こっているかとか、著作権侵害と具体的にどう闘うかなんて、やっぱり人間が手と足と頭と口を使わないと集められない情報を扱っているからなのかな、と。
とはいえAIについて静観しているのも、不安を募らせるばかりというのも違うよね、と感じています。今回はそんなことを考えながら読んだ3冊を紹介します。
AIの「間違い」を利用する-ー『創るためのAI』
そもそもAIとは何なのか、何ができて何ができないのかを「思考する機械」の開発の歴史を見ながら解説してくれます。私のように「何だか分からないけれど、流行っているので最近ChatGPTを触り始めました」というレベルの人にもお勧めできる分かりやすさと安心感があります。
いま店頭に並ぶ生成AIの本は「AIに期待通りの仕事をさせる方法」や「間違った答えを出力させないプロンプト(AIに仕事をさせるときの指示)の書き方」を指南するものが多いですが、この本ではさまざまなアーティストがAIならではの「間違い」や「自分が思ってもみなかったようなアウトプットを出してくること」を作品づくりに生かす様子が描かれています。
たとえば著者の徳井さんはDJをするそうなのですが、長年やっていると選曲や曲の繋ぎ方がどうしてもマンネリ化する。そこで「AIと自分が1曲ずつ交互に曲を選んでかける」という実験をします。「直前にかけた曲と近すぎず、遠すぎもしない雰囲気を持った曲をかけていく」という一般的なDJのセオリー通りのシステムにしたものの、AIは自分が思いもつかなかったような意外な曲を選んでくるのが面白い、というように。
他にも、AIの文章生成モデルが「文章の意味を理解しているわけではない(よくある言葉の組み合わせを提案しているだけ)」という性質を生かして、著者には思いつけなかったプロットや言い回しを取り入れ、AIと “共に” 小説を書いている例などが紹介されていました。シュルレアリスムの作家が半分眠りながら出てきた言葉で詩を書いたり、ウィリアム・バロウズやデビッド・ボウイがカットアップの手法を用いて「偶然性」や「不確実性」を取り込もうとしたことを、AIを使って試みている、というわけです。
AIは自らの手だけで作品を作り出せる機械でもないし、人間に言われた通りのことが完璧に実行できる機械でもない。徳井氏は使う人がAIを完全にコントロールしようとするのではなく、自分の想像力の限界を超えるために「存在することすら知らなかった『外部』から掬い上げるためのツール」としてAIを捉えることを提案しています。

「AIの間違いを利用する」をテーマにAI(Adobe Firefly)で作成したイメージ
AIが奪っていくものは何?-ー『霧のコミューン』
それでも「本当にAIに頼っていいのだろうか?」という漠然とした不安を捨て去れない人も多いのではないでしょうか。しかしAIのパワーと進化は凄まじく「AIを利用しないのは蒸気機関車が発明されたのに人力車にこだわっているようなもの」と言う人もいます。そういえば私が大学生だった25年前にはまだ「ネット上の記事を参考文献にして論文を書くなど認めない」と言っていた先生もいたんですよ。今では考えられないですが、AIもきっと誰もが息をするように使うようになるのでしょう……。
という憶測を「単なる現状追認、思考の放棄だ」と厳しく糾弾するのが今福龍太さんなのでした。今福さんは生成AIが吐き出す文章は「凡庸な総覧的要約」であり「もっともらしい事実の羅列」であり、かつ「多くの出鱈目を平然と輩出し、自らが回答するテクストにいっさいの倫理的な責任を取ることもない」といいます。レイシズムやセクシズムに満ちた言説もそれ以外の言説もフラットに並べられ、「オープン」とか「フリー(無料)」という甘言に騙されて個人のデータを搾取され、結局はGAFAのような巨大企業に隷従する人間を生み出しているだけだ……と容赦しません。「使ってみなければ、その技術の本性を見抜くこともできない――こうした現状追認的相対主義は、一見正論のように聞こえるものの、私たちの言語理性の水準が既に生成AIの指向するプラットフォームによって徹底的に零落させられている」と。AIの「間違い」を利用するためには私たちが何が「間違い」なのかを知っていなければならないですが、はたして自分はそのレベルに達しているのだろうかと不安になってきました。
もう一つ気になったのはエネルギーに関することで、人間ならば極めて少ない情報でも有効なアイデアや仮説が導き出せるのに対し、AIは膨大なデータを呑みつくすための巨大なデータセンターなしには成り立ちません。AIが機械学習をする際には莫大な電力を消費し、凄まじい量のCO2を排出するとか。
半導体大手のNVIDIAのCEOは「AI競争に勝つには原子力なしでは不可能だ」と言ったそうで、そこまでしてAIを発展させる必要って本当にあるのかな……?と思ってしまいます。
まあ、この2つの記事もperplexityっていうAIに探してきてもらったんですけどね……。

「AIが奪っていくもの」をテーマにAI(Adobe Firefly)で作成したイメージ
「深く読む」とはどういうことか-ー『デジタルで読む脳×紙の本で読む脳』
ただ、私たちの批判的思考の衰えは、残念ながらAIの台頭に始まったことではないのですよね。