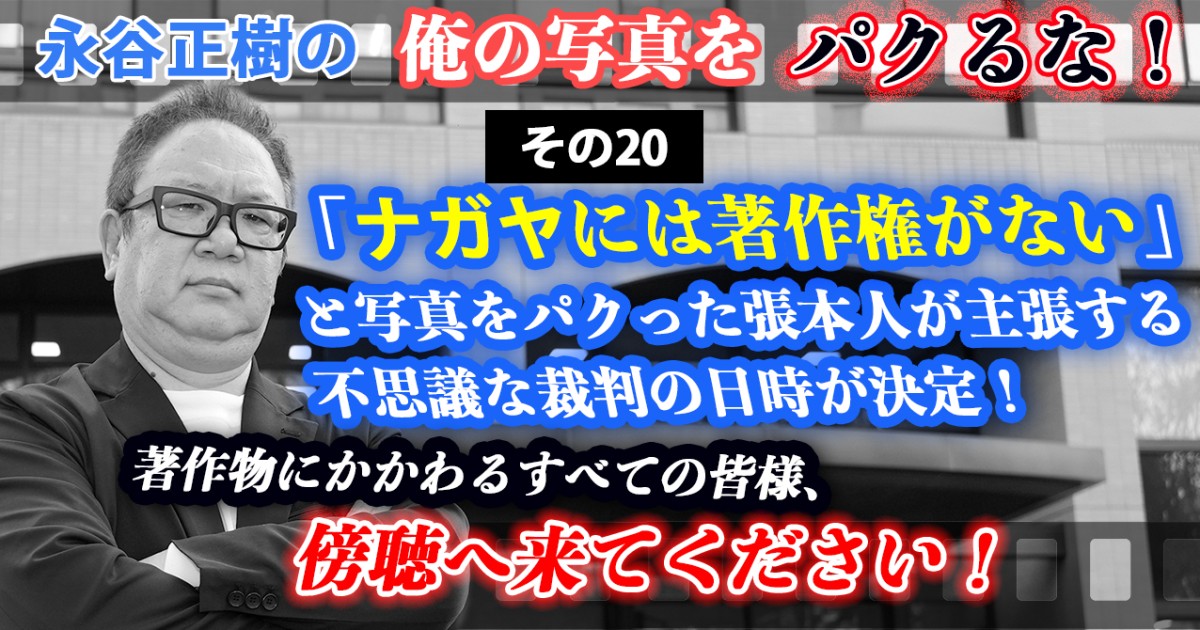石黒好美の「3冊で読む名古屋」③本棚が世界だーー『名古屋とちくさ正文館』
【今回の3冊】
・『名古屋とちくさ正文館』(古田一晴、論創社)
・『生活フォーエバー』(寺井奈緒美、ELVIS PRESS)
・『見えないものを集める蜜蜂』(ジャン=ミシェル・モルポワ、思潮社)

読者は本棚づくりの共犯者
本棚が世界なのだ。
各国の文学から日本の古典、俳句や短歌の棚から社会学、宗教、政治、哲学、精神医学へ。名古屋の郷土史や地理のコーナーには自費出版のミニコミ誌まで揃えられ、クラシック、ロック、ジャズから電子音楽、ヒップホップまで目配せした音楽批評本と落語や演劇の棚が隣り合っている。
めくるめく知の連関である。本を集めて並べることは、見たことのなかった世界をたちまち立ち上げることなのだ。

7月末で閉店が決まった名古屋随一の老舗書店「ちくさ正文館書店」(筆者撮影)
千種駅のほど近く、「ちくさ正文館書店」の人文・社会書のコーナーは書店員の古田一晴さんの手によるものだ。さまざまなジャンルの本を独自の視点でキュレーションした棚は「古田棚」と呼ばれ、全国から書店員が見学に来る。その本店が7月いっぱいで閉店するという。ホームページには店舗建物の老朽化のためとあるが、駅前にあった学習参考書専門店と本店が合併するなど少しずつお店をダウンサイズしていたから、いかに正文館といえどもやはり厳しい時代になっているのだと痛感せざるを得ない。
古田さんがちょうど10年前に書かれた『名古屋とちくさ正文館』を開く。ちくさ正文館は、文学に精通し出版業界にも豊かな人脈を持っていた谷口暢宏氏によって1918(大正7)年に開かれた。詩や絵画といったモダニズム運動の影響を受けながら、まだほとんど知られていなかった時代の塚本邦雄を自社のPR誌で特集し店で講演会を開くなど、当時から本を売るだけにとどまらない、名古屋の文化的な情報の集積地であり発信地だった。
高校時代から映画や演劇などのミニシアター運動に関わっていた古田さんは、大学生だった1974(昭和49)年にちくさ正文館でアルバイトを始める。社員となった後もこの地域の映画や演劇、詩や小説のシーンと関わりを持ちながら、その知見と人脈を生かして魅力的なブックフェアを企画し、店頭の棚づくりに反映させてきた。名古屋で上映される映画や演劇、ライブがあればそれらを軸にフェアをする。「市内の数カ所で同じテーマで表現方法の違うイベントを同時に行っている展開って、とっても面白いじゃないですか」。そしてこうした面白いことを一緒にやろうよ、というつながりは「名古屋くらいの広さだからできる」とも。「古田棚」は、古田さん自身の博識ぶりに加え、こうした書店の内外との交流や対話から生まれていたのだ。
90年代からは圧倒的な品揃えを誇る郊外型の大型書店が市場を席巻した。古田さんはPOSレジのデータばかりに頼った仕入れで書店の魅力がなくなり、書店員が育たなくなったと指摘する。以前に古田さんの講演を聞いた際には「棚は客と共謀して作るもの」と言っていた。書店員は客と会話しなければいけない、読者を育てなければならない。書店員と読者のコミュニケーションによる、本をめぐる知の集積が棚であり、書店なのだと。
それから10年、いまや本の買い場も売り場もAmazonに侵食され、POSレジのデータどころの騒ぎではない。「自分の嗜好に合った本をおすすめしてくれるだけ」なら、書店員は要らないのだろう。
生活と思想とユーモアを分けない
やはり書店に行かねばならぬ。
忙しいとか時間がないとか言い訳して、ワンクリックで本を買っては積んでいたくせに、ちくさ正文館の閉店の報に一丁前に落ち込んだ私は、今さらながら毎月必ずリアルの書店に足を運ぶと心に誓った。