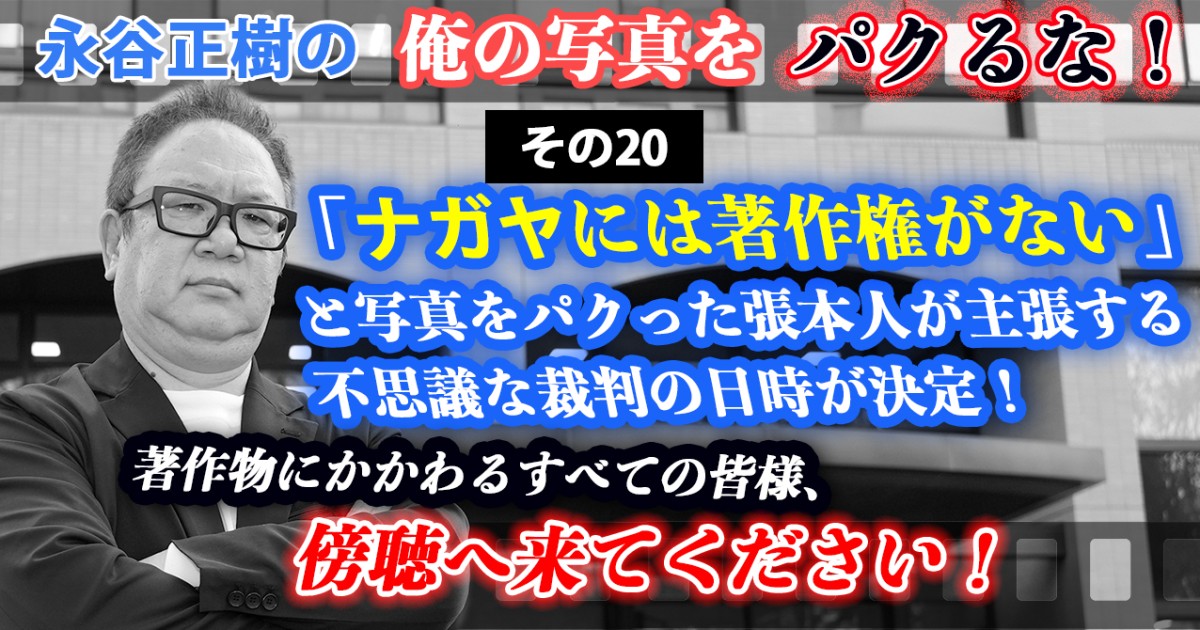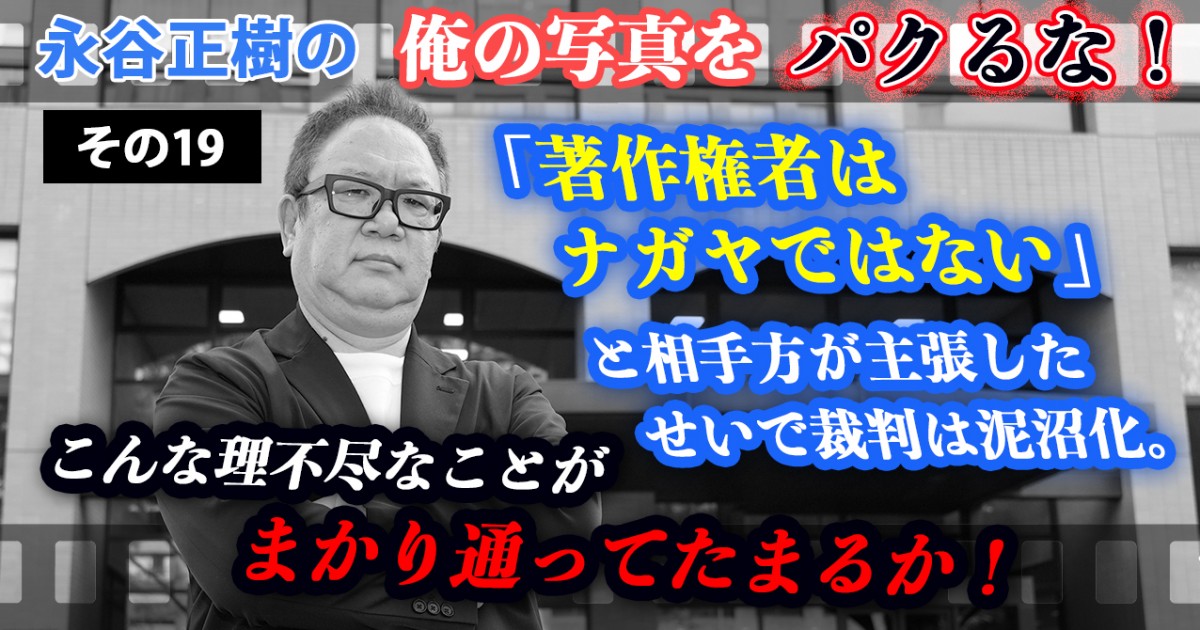クラブで遊びまくっていたら社会福祉士になった・石黒好美の「3冊で読む名古屋」【番外編1】
I Dance Alone
クラブはなぜ朝の3時や4時に終わるのか? 始発までどうしろというのか。90年代には今ほど24時間営業の店はなかったし、あったとしても高校生だった私はそこで過ごせるだけのお金を持っていなかった。店員の目を気にしながらコンビニを冷やかし、あてどなく栄やら大須やらどこだか分からないところを歩き、シャッターの開いていない地下鉄の入口の階段に座ったりしてひとり朝を待った。
ぞっとする遊び方だけれど、それでも私はクラブに行きたかった。友達を誘おうとは思わなかった。入場料に付いてくるドリンク1杯で閉店まで粘り、寒さに震えて岐阜行きの始発を待つのに付き合ってくれるとは思えなかったし、付き合わせたくもなかった。そうまでしてなぜ自分がクラブに行きたいのか、クラブの何が楽しいのか、誰かに説明できる言葉も、私はまだ持っていなかった。
ステージ上のミュージシャンと観客が向かい合い、観客はひとり残らずステージの上のミュージシャンを凝視(みつ)めていたコンサートより、だれもが好きな方向を向いて踊るクラブに、わたしは惹かれるようになっていた。
でもその「快楽」というのは、自分で楽しめる人しか楽しめないものでもある。誰かに楽しませてもらおうなんて考えてたら、いつまでたっても楽しくならない世界なのだ。
むしろ、ひとりになりたくて出かけていたのだ。家でも学校でも人からどう見られるかばかり気になって、過剰に優等生らしくしたり、反動で変な服を着てエキセントリックな言動をしてみたりする自分が嫌だった。クラブに行くとサラリーマン風の人も昼間に何をしているのか分からない系の人もそれぞれに楽しそうにしている。職業とか年収とか年齢とか容姿がどうとか誰も気にしない。私のことも誰も見ていない。

踊ってもいいし踊らなくてもいい、飲んでもいいし飲まなくてもいい。誰も他人のことなんて気にしないけれど、この場を共にする者どうしの暗黙のマナーや押しつけがましくない連帯感はあって、それがパーティを心地よく、熱くしていく。集団の中で自分が自分のままで居られて、誰にも干渉されないという経験は田舎育ちの私には新鮮で、なんて洗練されて、それでいて不埒な遊び方だろうかとしびれた。
普段の自分から離れて、ありたい自分で居られるクラブの暗闇は心底ほっとした。大人になっても楽しいことなんか何もないと思っていたけれど、終電から始発の間に、好きな音楽に包まれてこんなに解放される時間があるなら、それだけで十分生きていけるような気がした。

1995年に「世界初のテクノ専門誌」を謳って創刊された雑誌『ele-king』。創刊号はLPレコードと同じ12インチサイズ。
『ビッグイシュー』との出会い
就職氷河期をサバイブし、数々のライバルを蹴落として正社員の職を得た私は、朝から夜まで身を粉にして働いた。仕事が面白かったというのもあるけれど、そうしなければ社会から振り落とされるという恐怖感が大きかった。結婚も出産も絶対にしたくなかったし、できるとも思っていなかったので、とにかく自分で稼いで自分を食わせなければと必死だった。平日は深夜に帰宅し泥のように寝るだけの毎日だったけれど、週末には復讐するかのように爆音の中で夜通し遊べればそれでよかった。
30歳を前に、さらなる高収入を求めて名古屋に転職した私はボーナスで初めてイタリア製のバッグを買った。都心のオフィスに出勤し、自分の稼ぎでひとり暮らしをし、その上家賃より高いバッグまで買えてしまう。「自立した大人の女」になったように感じて、有頂天でブランドの紙袋を抱えた私は、名鉄百貨店の前で『ビッグイシュー』を売っている人を見かけた。
『ビッグイシュー』は「ホームレス状態にある人」だけが販売できる雑誌だ。お金やモノを与える援助ではなく、仕事の機会を提供することでホームレス状態にある人が生活を改善していくことを目的として、イギリスで生まれた雑誌だ。日本版は2003年に創刊され、現在も全国の駅前や繁華街などで販売が行われている。
テレビで紹介されていたのは知っていたけれど、売っているところを見たのは初めてだった。自転車の荷台みたいなものに雑誌を並べたおじさんにドキドキして近づき、一冊買った。帰りのJRの中で読みながら、学生時代から大好きでよく読んでいたクラブ・ミュージックの雑誌『ele-king』で見た記事を思い出していた。
デトロイトに住む黒人の多くは、社会的な地位からも富からも遠い存在としてこの世に生まれてくる。彼らは白人のように一生懸命に勉強したところで、将来が保証されているわけではない。それどころかゲットーでは、社会的に弱い者同士がお互いを傷つけあうことすらままならない。まるでこの社会では、自分は必要とされていないのに生まれてきたような気持ちを味わう。こういうなかで彼らが生きていくとき、頼りにするのは自分たちのソウルしかないのだ。着ている服や住んでいる家なのではなく、すべてを奪われてもまだそこに残されたもの。それがソウルだ。
クラブで聴いて大好きになったデトロイト・テクノやハウス、ヒップホップといった音楽は、まさに社会的な地位からも富からも遠い存在として生まれた人たちが作ったものばかりだ。人種や性別、性的指向や出身地などによって理不尽に差別され排除されてきた人たちでもある。
彼女ら彼らはそんな厳しい状況の中でも、夢のように美しい音楽や心を奮い立たせる逞しいビートを、想像力を駆使して創り出してきた。そうすることで自分たちの生を誇示し、差別や貧困を生む構造から目を逸らそうとする社会に激しく抵抗してきた。だからこそ国境も超えて多くの人の心を動かしてきたのだ。
私も女だからとか、くだらないことで人生が決められることや、差別はいけない、人は平等だと言いながら実際にはほとんどそれらが建前である社会に大きな戸惑いと激しい憤りを感じていたはずだ。それなのに、今の自分はすっかりそんな葛藤をなかったことにして、金を稼ぐためだけに生きている。自分はスーツやハイヒールに身体を押し込めて、社会に適応できているふりをしているだけではないか。対して、ビッグイシューの人は街頭に立って、自分はホームレスです、と偽ることなく打ち明けて、まっすぐに人生を拓いていこうとしているように見えた。
それはホームレス支援か
以来、「ビッグイシュー名古屋ネット」というグループでボランティアをするようになった。その日の売り上げを原資に、翌日に売る雑誌を仕入れに事務所に来る販売者さんに雑誌を渡し、お金を受け取る。こんなお客さんが来たとか、全然売れなかったとか、ジョニー・デップが表紙だとなぜ売れるのかとかを話す。
あちこちの学園祭や講演会などに呼ばれて一緒にビッグイシューの出張販売に行ったり、その後は打ち上げに行ったり、打ち上げなくても販売者さんや他のボランティアと一緒に飲みに行ったりした。年越しにみんなでおでんを食べようと鍋いっぱいに作ったら盛大に失敗して「まずい」とけちょんけちょんにけなされたこともあった。ボランティアの日は大急ぎで仕事を終えて事務所に駆けつけた。どこに行くのもいつもひとりで、さほど友達が欲しいとも思わなかった自分が、なぜこんなに人と関わる活動に夢中になれるのか、不思議なほどにのめり込んだ。

イベントでのビッグイシューの出張販売の様子(2010年頃)
一方で仕事は厳しくなった。IT関連だったが、知識や能力があったわけではなく、若さゆえの体力と長時間労働で何とか仕事をこなしていたので、業界のめまぐるしい変化に早晩ついていけなくなった。リーマンショック後からは社内も取引先の雰囲気もギスギスし始めた。私のミスで失注し予算が取れないとき、切られるのは正社員の自分ではなく派遣社員の人たちだった。無理な納期も断れず、長時間労働がたたって心身を病んで辞めていくエンジニアも少なくなかった。ビッグイシューのボランティアをしてホームレス支援だなんて言っているけれど、ホームレスを生み出しているのは他ならぬこの私ではないか。
そして2011年3月11日、テレビに映る避難所の様子を見て、これからどれだけ多くの人たちが「ホームレス」になってしまうのかと戦慄した。そして、今の仕事は明日津波が来るとしても続けたいだろうかと考えると、翌日には思い立って、社会福祉士の資格取得コースのある大学の説明会に足を運んでいた。
エンパワメントして社会変革する
人がホームレス状態に陥る理由はひとつではない。仕事を失ったり、借金があったり、心身に障害があったり、家族がいなかったり、学校に行っていなかったり、そのどれでもなかったり、これらの全部を抱えていたりする。社会福祉士になりたかったというよりは、ホームレス状態にある人たちのことをもっと知りたい気持ちが強かった。