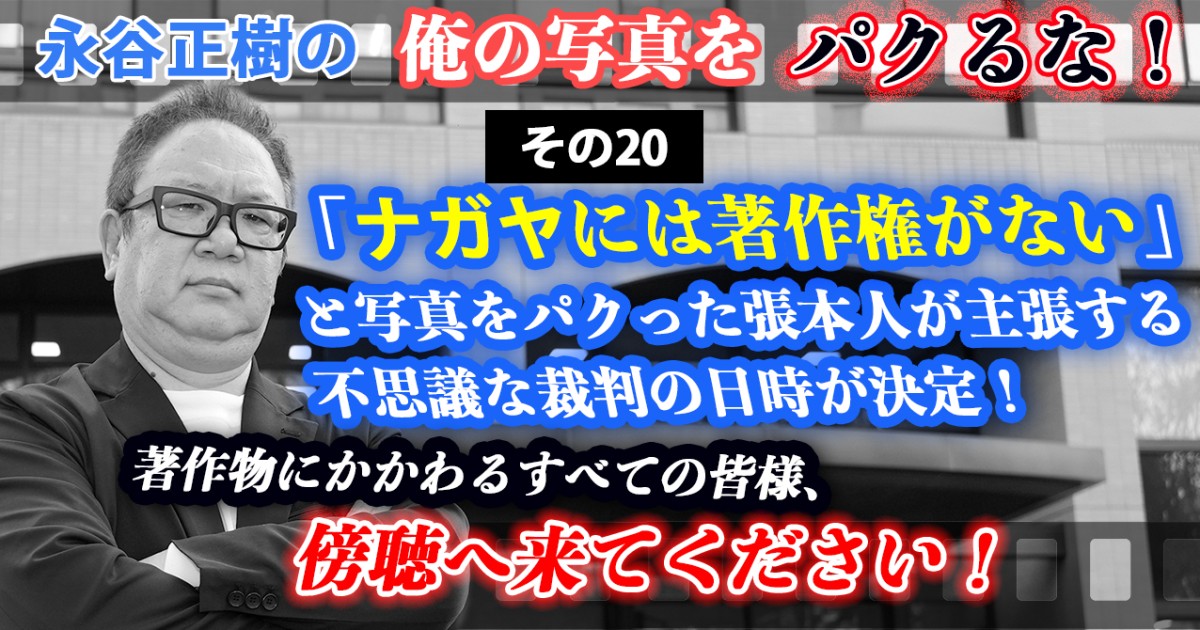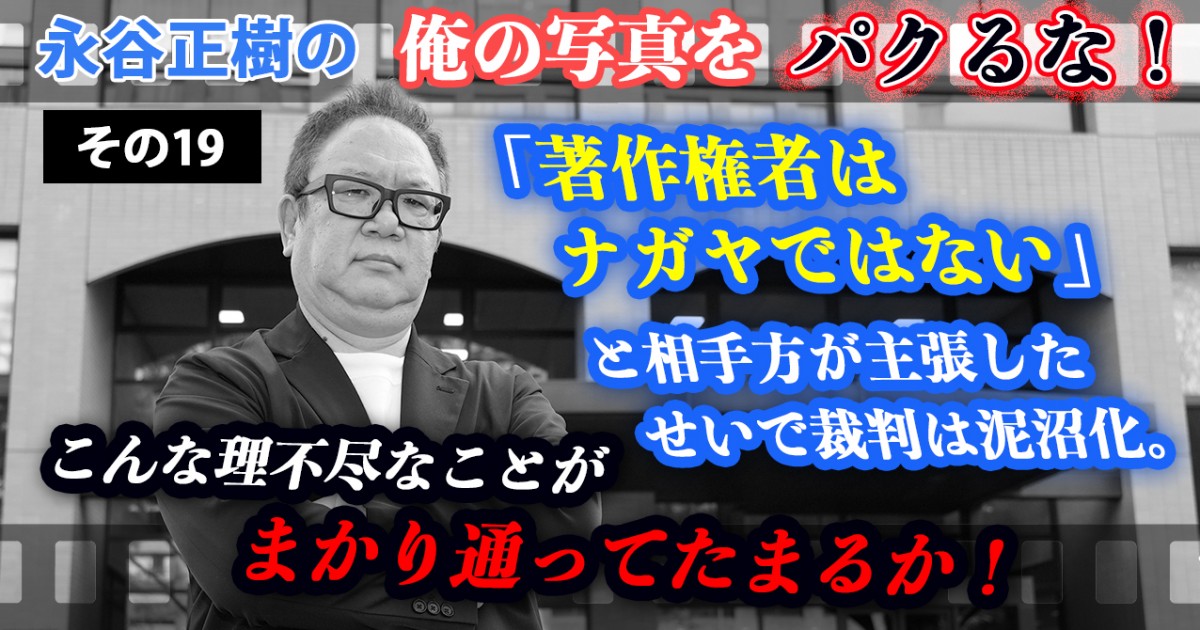【無料公開中】秦融の「メディア探策」〜『嫌われた監督』を読み解く④ ボレロの構成原理
鈴木忠平著『嫌われた監督』の魅力は、落合博満という人物の描き方にある、と、この連載の1回目に書いた。落合を取り巻く選手やコーチ、さらには著者自身が鏡の役割をして、そこに映る落合を多面的に描くことでこの難解な人物のぼんやりした立体像を作り上げている、と。今回は、同書が落合という野球人をより謎めいて描くことを狙った構成上の効果について書いてみたい。アライバのコンバートという監督在任中の「謎」を紐解く過程で、この謎めいた描き方が効果的に読めるのである。(文中、敬称略)

鈴木忠平氏著『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』(撮影・関口威人)
同書は昨年、いくつものノンフィクション賞を受賞したが、講談社本田靖春ノンフィクション賞はたまたま筆者の『冤罪をほどく』と同時受賞だったため、その選考過程について詳しく知る機会を得た。
選考委員は、魚住昭、後藤正治、最相葉月、中沢新一、原武史の五委員。関係者に配布されたB5判30ページの「要項」に各委員の選評があり、その中で「なるほど」とうならされたのが中沢新一委員の選評だった。こう書いてある。
『嫌われた監督』を読んでいて、途中から私は、これはラベルの「ボレロ」に似た構成原理をとっているな、と感じ始めた。各章ごとに少しずつ登場人物は変化していくが、きわめてよく似たパターンが繰り返されていく。パターンの中心は、クールな落合監督と、その彼に同一化したいという強い欲望を秘め持った作者の、交わりそうで交わらない男の愛の舞踏である。
実に言い得て妙である。
斬新さを見極める眼力とそれを一般化する表現力、さらには、著者と落合の距離を「男の愛」にたとえるという大胆で粋な喝破の妙に圧倒され、うならざるを得なかった。担当記者とプロ野球監督との関係を「男の愛」にたとえることも可能だとは、無粋な私には及ぶことのない次元の発想だった。
著者は同書の中で「自分と、自分が生まれた世界との間に確信が持てず、迷い続けている」と告白している。落合から醸し出される「謎」にその答えのヒントがあるのではないか、と予感するかのように、著者の8年間は始まり、断片的な言葉でしか語らない落合の中に至高のプロフェッショナリズムを見出す。そこに著者の追い求め続けてきた答えはあった。
文学作品をクラシック音楽に重ね合わせることが珍しいのかどうか、よくわからないが、誰もがどこかで聞いた覚えのありそうな「ボレロ」とくれば、あの独特なリズムとメロディが思い浮かぶ。
中沢委員評のこの一節に出会ってから、ユーチューブで何度もボレロを聴いた。音色と強弱を変化させながら、同じリズムとメロディがいつ終わるともなく続く。その泰然として粛々と流れる音楽には、まさに落合という野球人に抱くイメージと重なるものがある。選評を読み、ボレロを繰り返し聴き、私は「なるほどねえ」と感嘆の声を漏らさざるを得なかった。

ボレロはフランスの作曲家、モーリス・ラベルがバレエ団の依頼を受けて作曲したバレエ曲だという。
作品の筋書きは、スペイン南部に位置するアンダルシア州の州都セビリアの酒場を舞台に、一人の踊り子がゆったりと踊りだすところから始まる。初めのうち、客たちは見向きもしないが、踊りの高揚感が伝わり始め、酒場全体が惹きつけられるように、いつしか客たちも踊りだし、最後には全員が踊るというエンディングを迎える。
ボレロでは、小気味良いリズムを刻む打楽器に合わせ、管楽器がフルート、クラリネット、ファゴット、オーボエへと変化し、重なりあいながらメロディを奏でる。ソロから重奏、さらには合奏、そしてオーケストラの大合奏へと展開する。
『嫌われた監督』で楽器の役割を担うのは、選手やコーチ、ときには球団職員であったりする。
落合の監督着任からほどなくして開幕投手を言い渡される川崎憲次郎(第1章 スポットライト)、続いて森野将彦(第2章 奪うか、奪われるか)、福留孝介(第3章 二つの涙)と登場人物が入れ代わっていき、最後に荒木雅博(第12章 内面に生まれたもの)の出番が待っている。
ボレロがオーケストラの大合奏に向かって進むように、同書もまた、読み進むうちに前章、前々章の余韻が次の章のものがたりに重なり合うように進む。静かな落合の指揮によって登場人物たちが一つの調和を生み出していく。そんなチームの姿が読者のイメージの中で像を結びながら、当初はおぼろげだった落合という強烈な個性を軸とした集団の姿が次第に輪郭をはっきりさせ、最終章へと向かう。