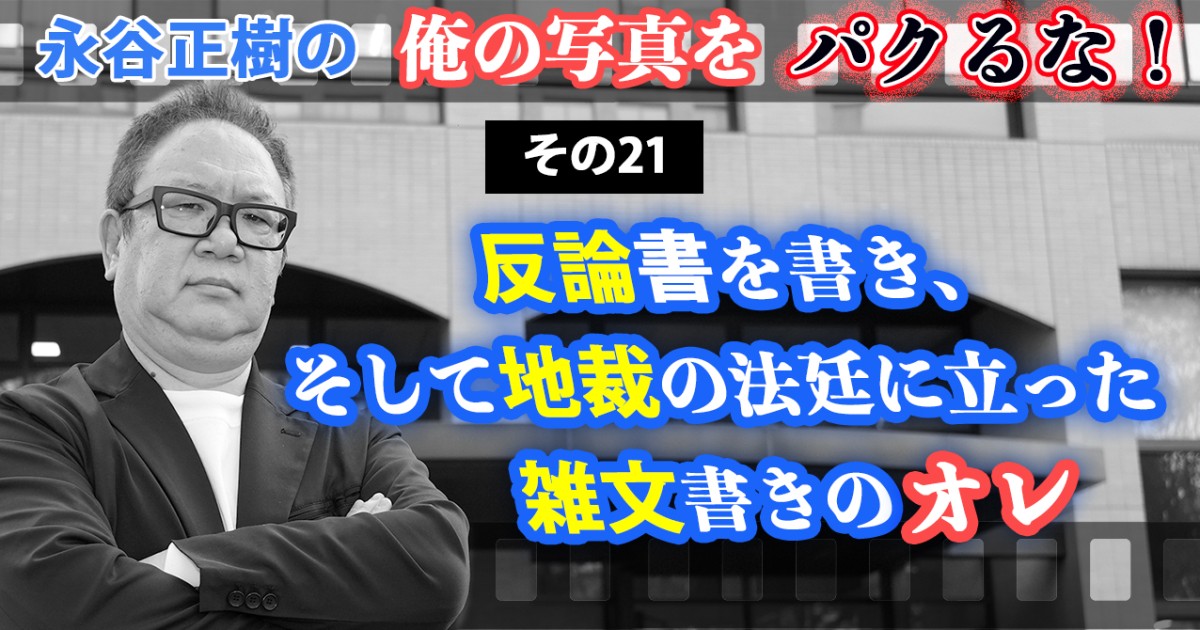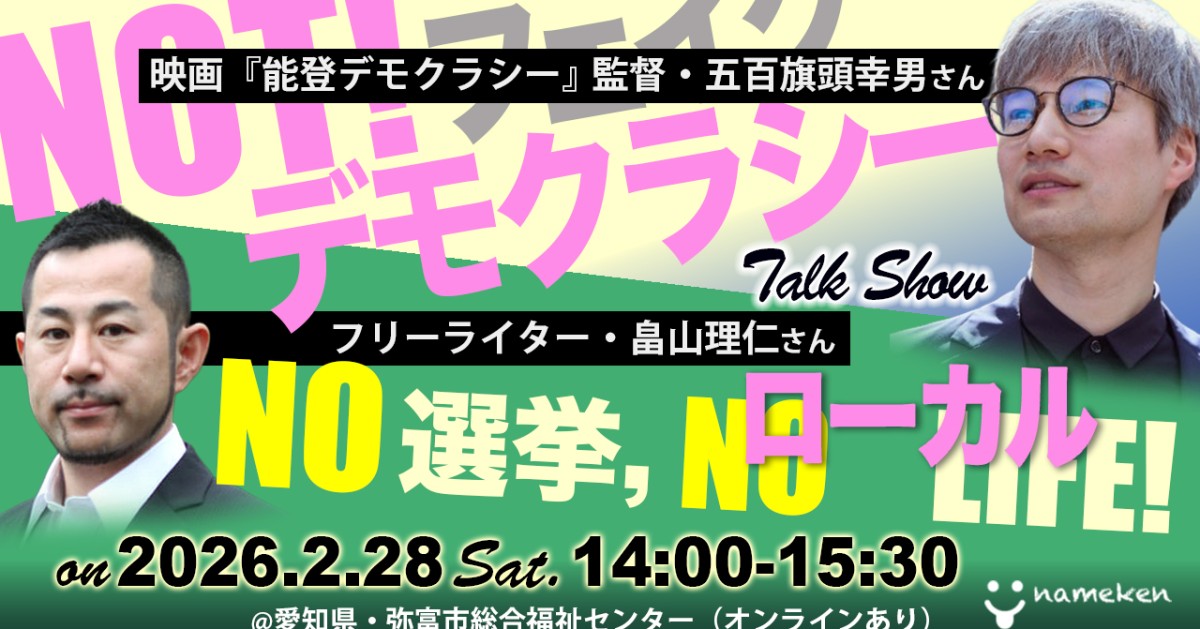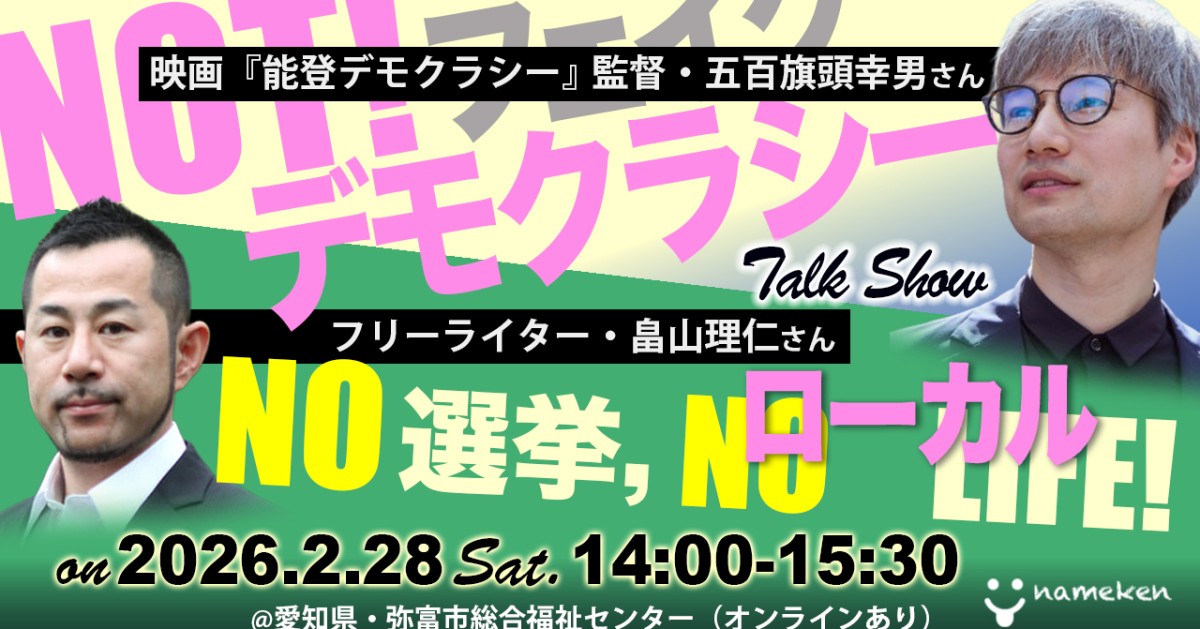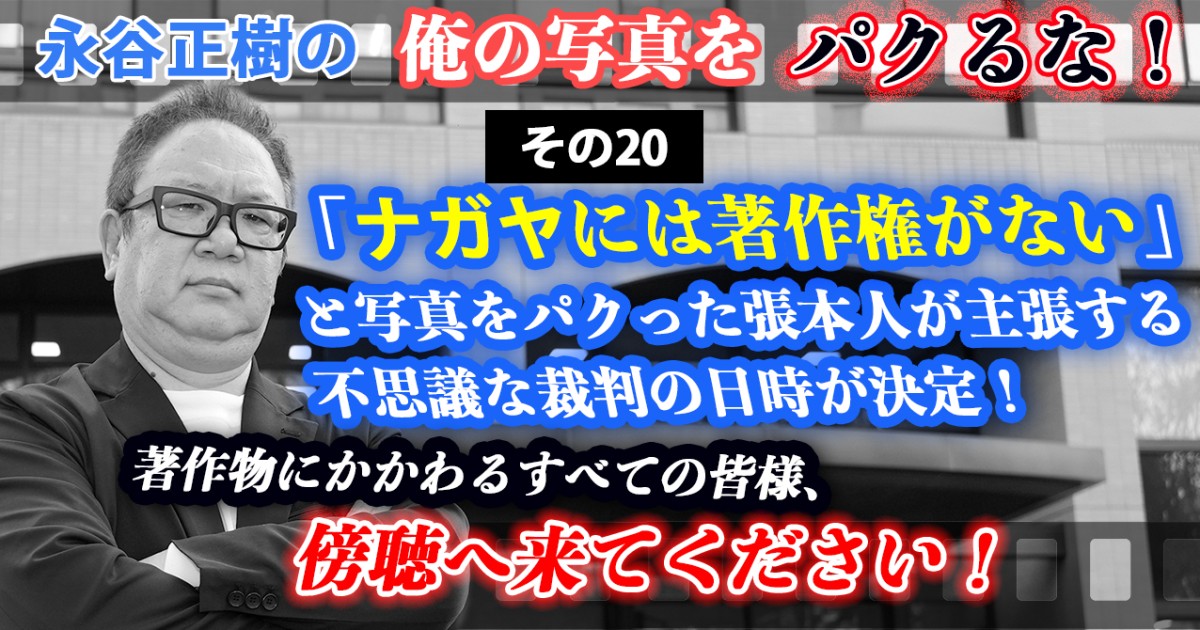石黒好美の「書く福祉」・大詰め迎える「いのちのとりで裁判」——生活保護基準引下げをめぐる裁判が問いかけるもの
国が2013年から生活保護費を大幅に引き下げたのは、憲法25条が定める生存権の保障に違反するとして、全国の29の地域で1000人を超える受給者たちが原告となり、国や自治体に引き下げ取り消しを求めて訴訟を起こしています。
「いのちのとりで裁判」と呼ばれるこの一連の裁判は、各地で「2013年の引き下げは違法」とする判決が出ています。今年3月末までに地裁では原告が19勝11敗、高裁では6勝4敗と勝ち越しており、原告の勝訴率が1割程度と言われる行政訴訟では異例の結果と言われています。国は敗訴した大阪高裁および名古屋高裁の判決について上告しており、5月27日には最高裁判所での弁論が決定、今夏にも最高裁判決が言い渡される見通しとなっています。

名古屋高裁での逆転勝訴を伝える「いのちのとりで裁判」原告側弁護団と支援者=2023年11月30日、筆者撮影
生活保護基準は厚労大臣の裁量で決められる?
原告はどのような点を「違法」であるとして争っているのでしょうか。裁判の主な争点は下記の通りです。
1)物価の下落率を意図的に大きくした「デフレ調整」
厚労省は削減した生活保護費の総額670億円のうち、580億円分は2008年から2011年までに物価が4.78%下落したことを反映させた「デフレ調整」によるものと主張しています。
しかし、厚労省が物価下落の根拠として採用した計算方法は特殊なものでした。消費者物価指数の算出に一般的に用いられる計算方式ではなく、なぜかこの時のみ物価下落率が大きくなる独自の方式を採用。統計学の専門家からも「厚労省の計算方式に学説上の裏付けはない」と指摘されています。
さらにはテレビやパソコンなど、この期間に物価の下落率が特に大きかった商品の影響が大きくなるよう計算していたことも判明しました。原告らは「物価の下落率を厚労省が意図的に大きく膨らませた『物価偽装』だ」として厳しく追及しています。
2)諮問機関の意見を聞くことなく減額した「ゆがみ調整」
厚労省は残る削減額の90億円分は厚労省の諮問機関である「生活保護基準部会」による検証結果をふまえた「ゆがみ調整」によるものとしています。これは所得下位10%層の消費実態と生活扶助を比較し、年齢・世帯人員・地域差による影響を鑑みながら基準額を調整するものです。
しかし、部会の部会長代理を務めていた岩田正美氏(日本女子大名誉教授)は、「ゆがみ調整」では扶助費をむしろ増額すべき世帯もあったと法廷で証言。にもかかわらず、厚労省は部会に無断で数値を2分の1にして計算し、全ての世帯を減額としています。
科学的な裏付けを欠く数値を根拠とし、有識者の意見も無視して「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する生活保護基準を厚労省の独断で切り下げてしまう――こんなことが許されていいのでしょうか。生活保護法の条文にはこうあります。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
原告は、厚労省の行った引き下げは2項にある「要保護者の必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たす」ものとは到底言えるものではなく、裁量権の濫用であると訴えています。
一方で国は第八条1項の「厚生労働大臣の定める基準により測定した」という部分をもとに、物価をどのように考慮するかも、生活保護基準部会の意見を取り入れるかどうかも、厚生労働大臣が定めればよいと主張。保護基準の設定は厚生労働大臣の裁量に委ねられているのだから、数値の統計学的な正しさや、専門家の意見も考慮する必要はない、と言っているのです。

時代によって変わる「最低生活の基準」をどう決めるか?
いくら法律に「引き下げの根拠には科学的な裏付けが必要です」「専門家の意見を取り入れなさい」と明文化されていないからといって、このような主張が許されるものなのでしょうか? ……許されないからこそ、各地で原告が勝訴しているのでしょうが、かといって「生活保護基準は、このように決めるべきである」と具体的に書かれているわけでもありません。
そもそも「健康で文化的な最低限度の生活」とは、どんな生活なのでしょうか?何がどれくらいあれば「需要を満たすに十分」なのでしょうか。
たとえば1957年(昭和32)に起こされた生活保護に関する裁判「朝日訴訟」。当時の生活保護の日用品費は月600円、「シャツは2年に1枚、パンツは年に1枚」という基準でした。服はボロボロでも、肉体的には死んでいないのだからいいじゃないか、という考え方です。このように「最低限度の生活」の基準は当時の社会の「貧困観」と結びついて時代とともに移り変わってきました。
社会が豊かになるにつれ広がってきたのが「相対的貧困」という概念です。生命が維持できるのみならず「その社会で当たり前とされる生活ができない状態」を貧困とみなすものです。エアコンが買えないとか、子どもが修学旅行に行けないとか、食事は取れていても栄養は足りないといった状態が挙げられます。加えて近年では特に「社会参加が妨げられている状況」も「貧困状態にある」とみなされるようになりました。収入や資産がないために友人や家族との集まりに行けなかったり、祝儀や香典を用意できず冠婚葬祭に参加できなかったりする状態です。
こうした貧困観の変遷に伴い、生活保護基準の考え方も変化してきました。1983年(昭和58)の中央社会福祉審議会の答申では、食費はもちろん生活全体にかかる費用が、生活保護世帯においては一般世帯(生活保護を利用していない世帯)の60%程度の水準に達する状態を維持しよう、とされました。
この考え方は現在も引き継がれていますが、1983年といえばまだ日本経済が右肩上がりであった時代です。「一般世帯」の所得も低下している今、新たな生活保護基準の決め方が必要ではないか?とは、2011年(平成23)の生活保護基準部会から繰り返し指摘されていますが、いまだ実現に至っていません。
それどころか2019(令和1)年には所得下位10%層の生活水準と生活扶助基準を比較した結果、ほとんどの生活保護世帯でさらなる引き下げが行われました。この「所得下位10%層」には生活保護世帯が含まれていた上、日本の生活保護の捕捉率(生活保護の対象となるべき人のうち、実際に受給している人の割合)は20%程度ですから、所得下位10%層と比較すればどうしても「生活保護基準の方が高い」となり、保護費が下げられてしまいます。これでは「健康で文化的な最低限度の生活」に求められる内容は変わっているのに、生活保護基準は際限なく下落して、再び「朝日訴訟」時代に戻ろうとしているのではないか、と感じてしまいます。
生活保護基準の決定方法の見直しを
時代に合わせて柔軟に「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮」しながら最低限度の生活を決めていくことができればよいのでしょうが、残念ながらそうなっていない以上、生活保護基準の決定の方法にはもう少し詳細な規定が必要なのではないでしょうか。