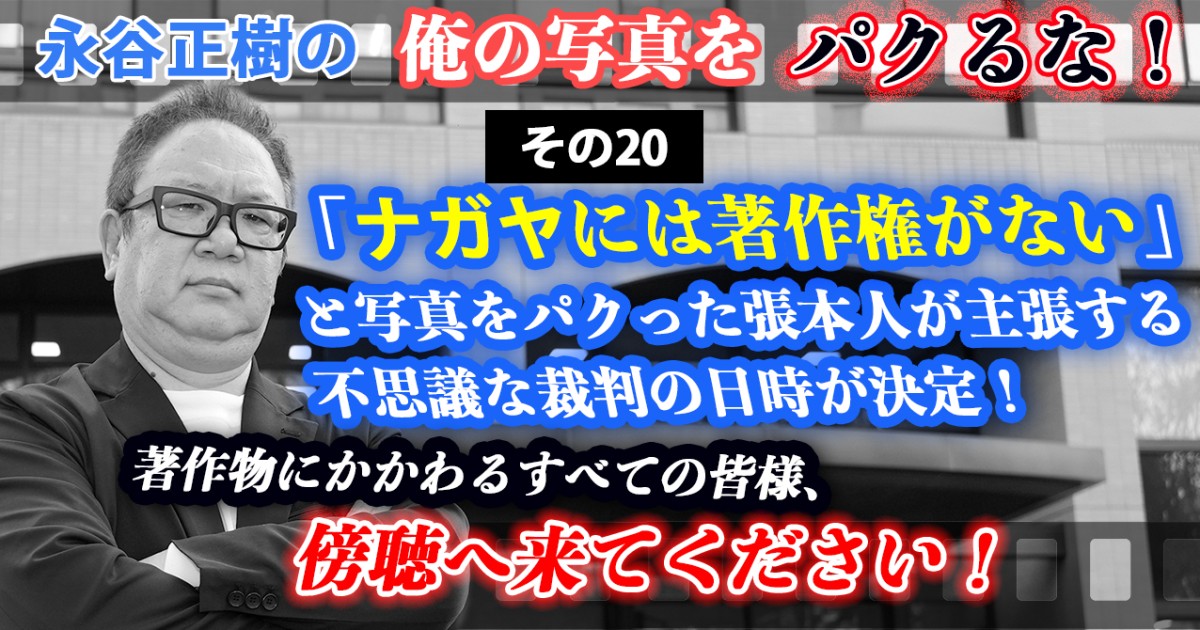石黒好美の「3冊で読む名古屋」②あわのまにまに
【今回の3冊】
・『あわのまにまに』(吉川トリコ、角川書店)
・『彼岸花』(青色ひよこ、トーチ)
・『夕暮れへ』(斎藤なずな、青林工藝舎)
「平成レトロ」がブームになっているという。ルーズソックス、ガラケー、たまごっち、厚底の靴、プリクラ、iMac…。キムタクがA BATHING APEを着て、ポケベルのCMに広末涼子が出ていた、1990年代のグッズやカルチャーが「エモい」とZ世代にもウケているらしい。
昭和生まれとしてはつい最近のようにも思うけれど、もう20年以上も前なのだ。かくいう私も若い頃には、60年代や70年代の音楽や流行を語る親世代を見ては「いつまでそんな昔のことにこだわっとるんやろ?」と不思議に感じていた。
でも、40歳を過ぎた今なら分かる。何十年が過ぎても、薄れるどころかいまだに生々しくひりつく、ビビッドな記憶があることを。
私たちは「ロスト・ジェネレーション」と呼ばれる世代だ。物心ついた時には燃え尽きる寸前の線香花火みたいに一瞬だけ世の中がバブりまくったと思いきや、10代の半ばからはずっと落ちていくばかりの日本で育った…と、言われている。

わが家の愛猫、漱石先生(筆者撮影、本文とは直接関係ありません)
人生はサバイバルだと思ってきたから、生き残るためにとにかくがむしゃらにやってきた。氷河期世代の私が一度も職に困ったことがないのは、要領よく立ち回って他人を蹴落とし、会社の都合に合わせて非正規労働者を集めたり切ったりしてきたことの成果だ。けれどそうして44歳になって、自分に何が残っているというのか。大した貯金があるわけでもなく、相変わらず未来は暗いままで、今では自分が振り落とされまいと必死に何かにしがみついている。
一切の同情拒否する白黒の物語ーー『彼岸花』
だからWebで連載中の漫画、青色ひよこ『彼岸花』には大いに打ちのめされている。押しつけられた規範はいらない、あたしの体も心もあたしのもの。暗闇や憎しみこそを音楽に込める、狂っているのはあたしじゃなくて、世界のほうーー。90年代はバンドでそう叫んでいたのに、40歳を過ぎた今、かつてのパンクスはバイトと派遣で食いつなぎ、コールセンターで客にも正社員にも見下され、マッチングアプリで売春し、一瞬たりともシラフでいられず酒や薬が手放せない。
そうなのだ。阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件がとどめを刺すように日本の風景を一変させたけれど、まだ90年代には瓦礫の中からこそ立ち上がろうという気概が、時代の中にあったように思う。自分たちのナマの言葉でリアルな生を表象しようとするラップ/ヒップホップだって乾いた地面を割って出てきたし、KEN ISHI『Extra』のビデオみたいに、テクノロジーで未来が拓けるはず、という楽観的な気分だってちょっとはあった。けれど、その青春時代の夢や理想や希望こそが、怨霊となって現在の自分たちを執拗に傷つける。『彼岸花』の、グラデーションのない白黒の線には一切の同情を拒否する鋭さがある。リストカットの傷跡を剥き出しにして歌う少女の激しさそのものなのだ。

(左から)Web漫画の『彼岸花』、斎藤なずなの『夕暮れへ』、吉川トリコ『あわのまにまに』(筆者撮影)