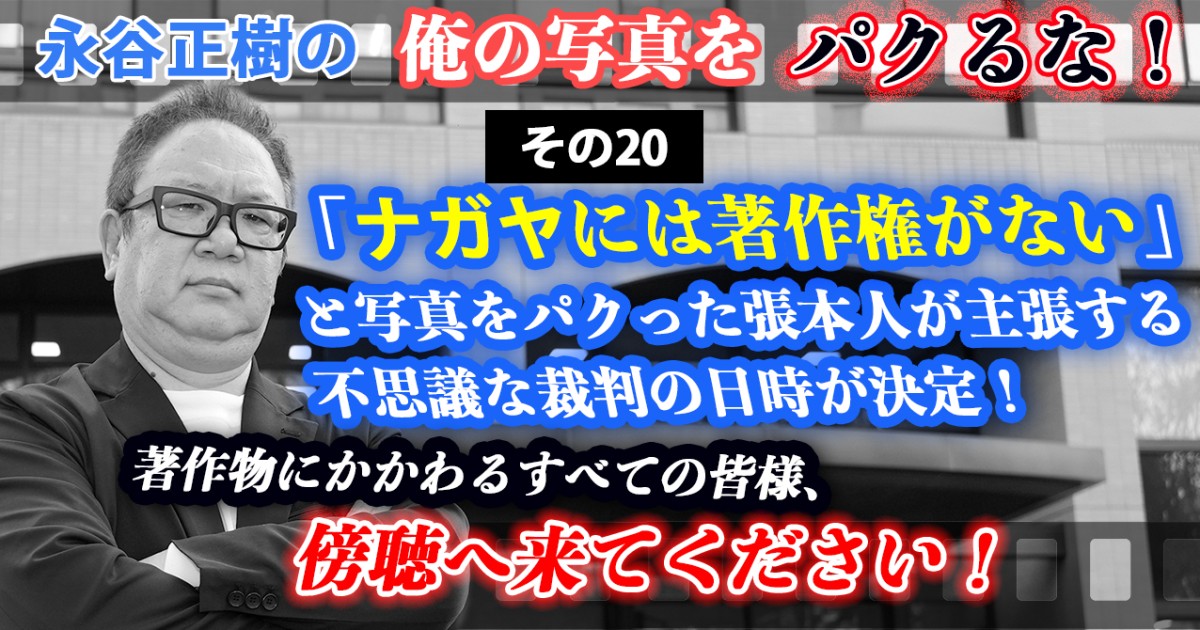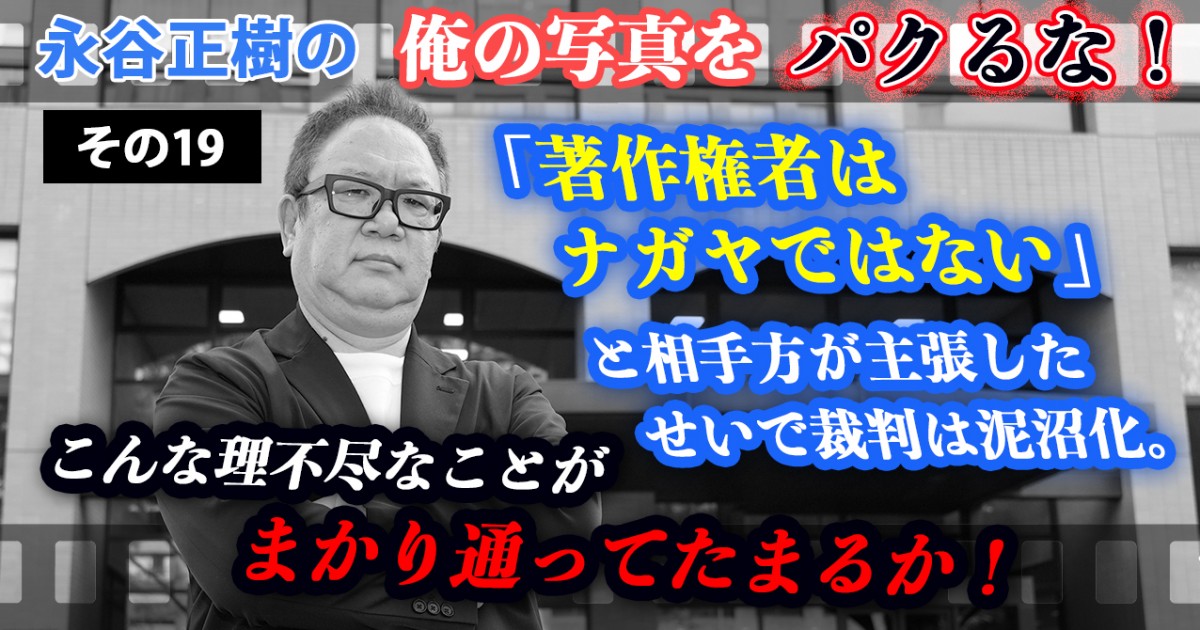阪神大震災と能登半島地震・落ちこぼれ建築学生が感じる30年目の使命
能登半島地震ではいまだに安否不明者が多数おり、大切な人や家を失った皆さん、先の見えない避難生活を過ごしている皆さんの心痛は察するに余りあります。
一方、17日には阪神・淡路大震災から29年の節目が来ます。1995年から数えて今年は30年目です。
あのとき建築学生だった僕は、テレビ画面に映し出される神戸の街の惨状と、自分が学んでいた建築デザインとのギャップにただただ茫然自失しました。
今、一介の物書きとして能登の被害を目の当たりにしています。29年前と同じ無力感を覚えながら、今なら自分に何ができるのかを考えざるを得ません。同じ悲劇が繰り返されないよう、あのときの経験から振り返ってみます。
下宿のテレビに映し出された神戸の街の衝撃
1995年1月17日午前5時46分。淡路島北部を震源とするM7.3の地震が発生しました。
全国的に冷え込みが厳しかった朝。僕は東京・雑司が谷の木造賃貸アパートの一室で、製図台の下に半分隠れるように敷いた布団から抜け出し、14インチ程度だった小さなテレビをつけました。そこには、黒い煙が何本も上がる神戸の街が映し出されていました。

地震直後にあちこちから火の手が上がる神戸市長田区のJR新長田駅南西付近から鷹取駅付近を写した空撮(1995年1月17日、神戸市のオープンデータサイト「1.17の記録」から)
当時、携帯電話(ガラケー)はありましたが緊急地震速報なんかは来ません。ちなみに東京は震度1だったようで、揺れも感じませんでした。しかし、テレビで叫ばれる神戸の震度は「6」。まだ地震の観測体制が整っていなかったので、後に「7」に修正されました。
僕はテレビの前であっけに取られながらも、やがて製図台に向かって図面を引き始めます。建築学科の4年生として「卒業設計」の提出が2月に控えていたからです。
建築を諦めて新聞社、ジャーナリストの道へ
建築もいろんな分野がありますが、僕が専攻していたのは意匠系、つまりデザインの分野。建築のデザインといってもいろんなレベルがあり、極めて大まかにいうと機能的だけれど無味乾燥な近代建築から、その反動として装飾性に回帰したポストモダン、そして90年代は部分を解体して全体を再構築するデコンストラクションなどへと向かっていました。
だから学生の間でもギザギザ、ガタガタ、クネクネのデザインが流行っていたのですが、それは現実に破壊された神戸の街に対して、あまりにも無意味でした。
それ以前にも、建築業界にはまだバブルの余韻が残り、派手な商業ビルや豪邸が建築雑誌の誌面を飾っていた時代。僕は団地住まいの貧しい家庭で生まれ育ったので、徐々に違和感が膨らみ、神戸のニュースを横目に仕上げた卒業設計の評価も大したことはなかったので、自分には建築の才能も適性もないのだと感じました。
だから予定通り大学院まで進学したものの、ずっと胸にはモヤモヤが。ちょうどその頃、研究室の先輩たちが建築の同人誌を発行し始めていたので仲間に入れてもらい、神戸で建築家たちが何をしているのか、自分なりに情報を集めて文章にまとめ出しました。
坂茂(ばん・しげる)さんの紙管建築をはじめ、テントやコンテナを使って仮設住宅やコミュニティーをつくろうとする動き。当事者にインタビューをして、半年以上経ってからやっと自腹で神戸の現地へ。
こんな活動が、その後の新聞記者業、そして今のジャーナリスト業につながっています。

震災で焼け野原となった神戸市長田区の鷹取商店街(1995年1月18日、神戸市のオープンデータサイト「1.17の記録」から)
「死者の声を聞け」という教えとは
今回の能登の地震では坂さんがさっそく紙管の間仕切りを避難所に提供。名古屋からは名古屋工業大学教授の北川啓介さんがダンボールなどを使った「インスタントハウス」を届けるプロジェクトを展開しています。
北川さんは東日本のときに牡鹿半島での支援活動を取材させてもらいましたが、その頃から突き詰めてきた建築による支援の形がどんどん洗練されてきました。意匠系の人間としては、こうしたデザインによる社会課題の解決にほれぼれとします。