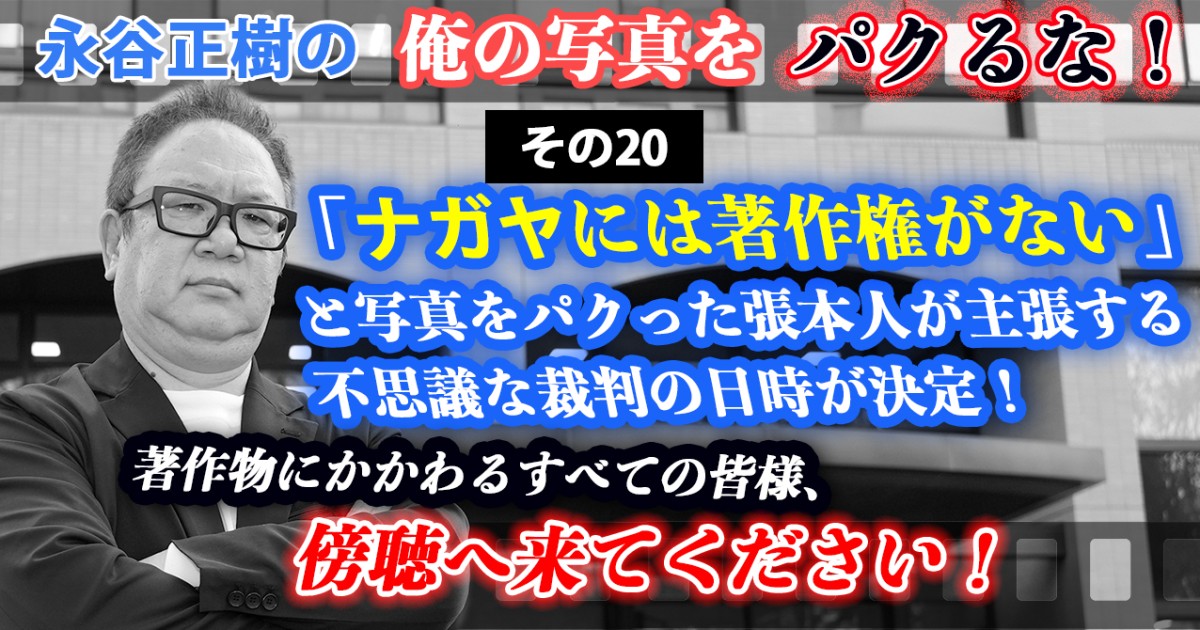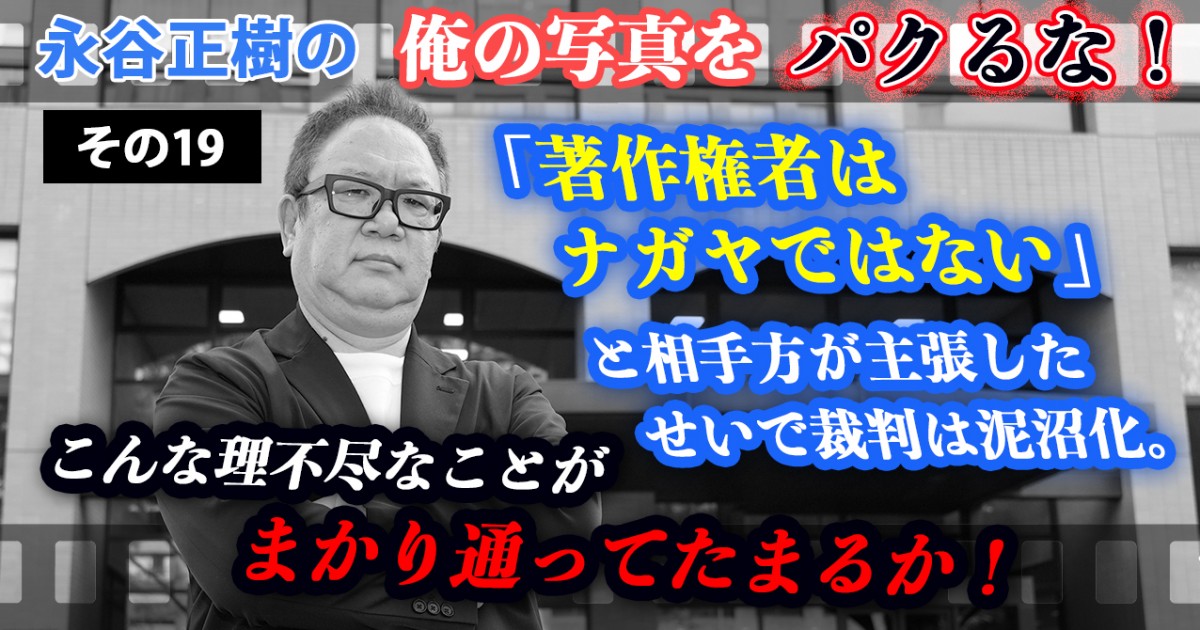石黒好美の「3冊で読む名古屋」①なごやボランティア物語
【今回の3冊】
・『なごやボランティア物語』(なごやのボランティア史編纂委員会、風媒社)
・『あそんでまなぶ わたしとせかい 子どもの育ちと環境のひみつ』(勝間田明子・細田直哉・佐治晴夫、みらい)
・『借りの哲学』(ナタリー・サルトゥー=ラジュ、太田出版)
贈与としての記録、読むという借り-『なごやボランティア物語』
ホームレス状態にある人や生活に困っている人たちを応援するボランティアを始めてから15年ほどになります。私は自分が関わってきたボランティアや福祉にまつわる活動をあらわす言葉が、どれも紋切り型でつまらないと感じていました。人の役に立てるのがうれしい。子どもやお年寄りの笑顔が輝いている。「ありがとう」と言われることがやりがい。どれも間違ってはいないのに、リアリティがない。活動を通して得られると思ってもみなかった体験や、心を抉るような感動、掴みづらいけれど確かに感じられる価値、といったものを、どう書けば伝えられるのだろうかと考えていました。
『なごやボランティア物語』は、「ボランティアの価値」を信じた人たちが集まり、実に4年以上の年月をかけて作られた本です。

名古屋地域のボランティア活動の歴史を一冊にまとめた『なごやボランティア物語』(関口威人撮影)
戦後から50年にわたる名古屋のボランティア団体の資料を保管していたのは、この地域のボランティアの草分け的存在である野村文枝さんでした。老親の面倒は家族がみるのが当然とされていた1970年代から、地域のお年寄り向けにヘルパーや食事を届ける活動を始めていたといいます。加えて、ボランティア団体同士をつなぎ、活動で得た知見を行政に提案し、公的な制度をつくることにも尽力されたというパワフルな方です。そんな野村さんの「名古屋のボランティアの活動を歴史としてまとめておくべき」という思いに共感した11名のNPOスタッフや社会福祉協議会の職員といった人たちが編纂(へんさん)委員となり、資料を読み込み25の団体に取材し、クラウドファンディングで約100万円の制作費の寄付を集め『なごやボランティア物語』は生まれました。
「あそんで、まなぶ」ボランティア
「ボランティアさんが来ると、社会がやって来る」
『なごやボランティア物語』の中で、知的障害者施設の顧問を務める方が語った言葉です。家族や施設の職員と障害者が「上下関係」になりがちなのに対して、ボランティアは友達として、あるいは一般の人として関われる。ボランティアがただ隣にいるだけで障害者の心が動き、社会とのつなぎ役になれるといいます。
ボランティアをする人にとっても、高齢者や障害者、子ども…といったさまざまな人たちとの出会いは新たな社会への扉です。元気がなさそうに見えた認知症の方と一緒に食事の用意をすれば見事な包丁さばきに驚き、被災地に通ううちに、最初は「助けなければ」と思っていた人たちが仲間に変わっていく。「子どもが育つまでは我慢」と思っていた母親が、自ら動いて子育て環境を変えていく人になる。職場や学校といった普段の生活では出会えない人たちと出会うことは、自分と人、そして社会との関わり方が変わるということです。関わり方が変わることで、自分や人、社会の見方が変わり、知らなかったことが見えてくる、分かるようになる、できることが増える。それこそがボランティアの価値であり、楽しさではないでしょうか。
それはまるで子どもが「遊び」を通じて自我や社会性を身に付けていく過程のようです。幼い子どもが積み木に触れると、徐々に「並べる」、「積む」、そして「ころがす」「投げる」「二つ持って打ち鳴らす」…といったいろいろな「遊び方」を自然と見つけていきます。『あそんでまなぶ わたしとせかい』では、これは子どもが「積み木」と「自分」の関係性をさまざまに捉え直しながら、「積み木」の可能性(使い道)を探しているのだと解説します。
ここで「積み木は積むもの」という考えにとらわれていると、遊びは広がりません。大人が「家を作ろう、車を作ろう」と指図してばかりでも楽しくなりません。「遊び」とは、自発的に、かついろいろに視点を変えながらモノや人のたくさんの可能性を探していくことなのです。
ボランティアもまた、実践してきた人たちにとっては「被災者は助けられる人」「母親は我慢するべき」「障害者だからできなくて当たり前」といった思い込みを揺るがし、新たな可能性を見出すことでした。ボランティアはまさに「わたしとせかい」を「あそんで、まなぶ」ことなのでしょう。
私たちは知らず知らずのうちに「こうしなければならない」という思い込みにとらわれているものですが、さまざまな人と関わることで「遊び」が生まれ、「これしかない」と思っていた現実に、新たな意味を見出すことができるようになります。だからこそボランティア活動から、先駆的な事業や柔軟でユニークなアイデアが生まれてきたのでしょう。

わが家の愛猫とらひこくんと漱石先生(筆者撮影、本文とは直接関係ありません)