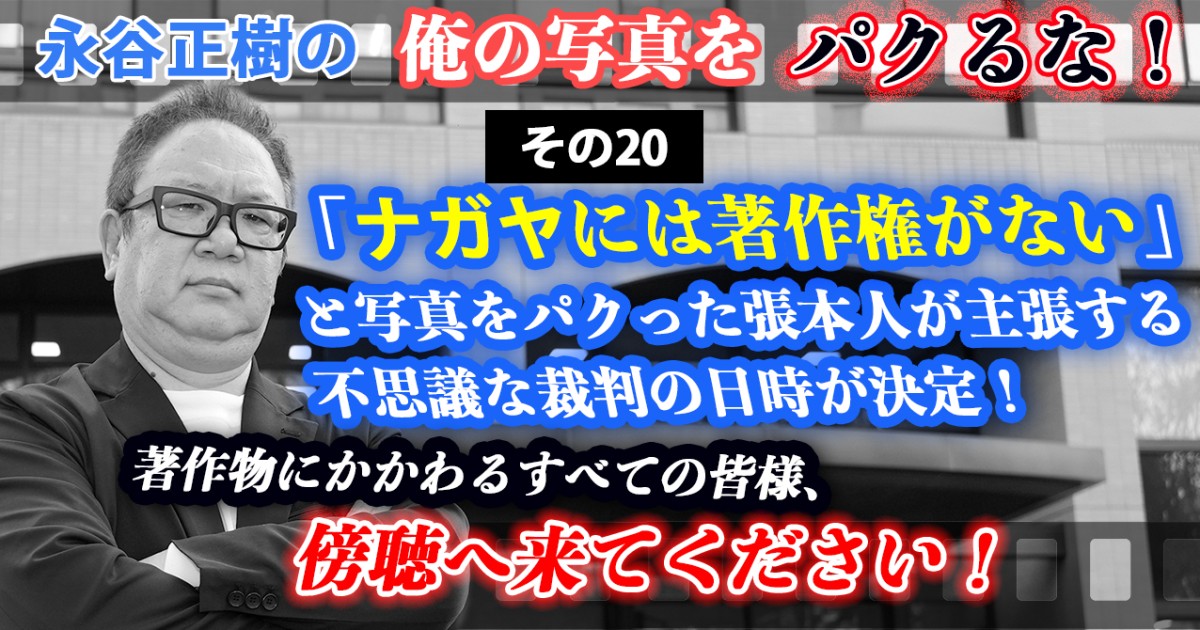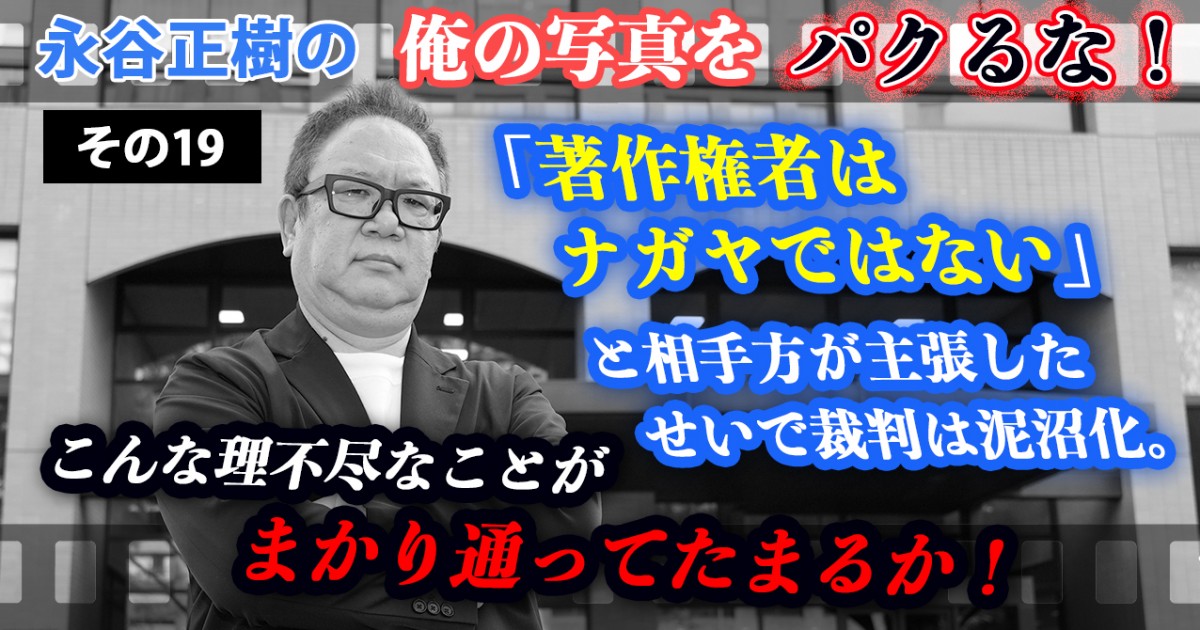【無料公開中】秦融の「メディア探策」〜『嫌われた監督』を読み解く③
『嫌われた監督』の魅力の一つは、監督落合博満が遺した「謎」の紐解き方の巧みさにある。その代表的な例として、今回は「アライバ」とファンに親しまれた黄金の二遊間を入れ替えた謎について、前回に続き鈴木忠平氏が著書の中でどのように紐解いてみせたか、たどってみたい。(以下、敬称略)

「アライバ」の一人、荒木雅博と落合博満の関係に迫る『嫌われた監督』の章(撮影・関口威人)
ところで、同書では全編を構成する中で、名セカンドとして何度もゴールデングラブ賞を受賞した荒木雅博が特異な存在感を示している。理由の一つは、著者が荒木と同年の生まれで特別に親しい関係だったからと思われる。
プロ野球の担当記者として、チームに食い込む突破口が「同級生」になることは少なくない。中日ドラゴンズで二十代に七年間、プロ野球担当記者としてのキャリアを積んだ私もそうだった。
私の場合、抑えのエースで、その後落合との1対4の交換トレードでロッテに移籍した牛島和彦、セットアッパーとして活躍した鹿島忠、投手から内野手に転向した仁村徹がそうだった。「同じ学年なんで、よろしく」。彼らとの出会いの場面は今も印象に残っている。記者と選手の関係を越え、飲みにもいったし、ため口で話せる間柄だった。縦社会の野球界では、年齢や学年による上下関係が基本になっているため、「同級生」は仕事の関係を超え、特別な間柄になりやすい。日本の野球界の特徴と言える。
著者と荒木もそのような関係だったのだろう。例えば、あるナイター後の夜ふけに荒木が著者の携帯に突然電話を掛けてきて、話し始めるくだりがある。
「今さ、本を読んでいて、いい言葉を見つけたんだ」
荒木は大抵、こちらの問いを待たずに話し始めた。
「千利休の言葉でさ、一より習い十を知り、十からかえるもとのその一っていうのがあるんだ。これ、今の俺にぴったりだと思わないか?」
自分に言い聞かせるような口調だった。エラーを犯した夜、ひとり眠れず葛藤しているのがわかった。
「監督はさ……、心は技術で補えるって言うんだよ。不安になるってことは技術が足りないんだって……。それはつまり、俺にもとの一に戻れって言っているのかな?」
同じ一九七七年に生まれた私は時折、荒木に自分を重ねることがあった。彼もまた自分と、自分が生まれた世界との間に確信が持てず、迷い続けているように見えたからだ。
守備位置の変更に苦悩する荒木の心情を深く、詳しく知る取材者だからこそ、彼が発する言葉の意味を悟ることができたのだろう。そして、著者はこの荒木の言葉から「アライバ」二人のコンバートの裏に潜んでいた落合の真意を導き出そうとさらなる取材を進める。
荒木が同書の構成上、重要な役割を担っているもう一つの理由は、本書の副題にある「落合博満は中日をどう変えたのか」の解そのものに荒木の変化を重ねているからである。それを追々紐解いていきたいと思う。
それまで、セカンドの名手としての名声を得た荒木は、指揮官のコンバート指令に深く悩む。その悩みへ、自ら答えを出そうと必死であがく。著者への電話は、そのプロセスでの一コマだったと思われる。
荒木の心が変化していくプロセスの全容を知るには、異色の監督落合との出会いからたどる必要があるだろう。本の中で、荒木と落合の出会いがこんなふうに描かれる。
どこか得体の知れない空気を漂わせた指揮官が、ノックバットを持って自分の前に現れた日のことを、荒木は鮮明に覚えていた。
それは落合が就任して間もなく、二〇〇三年秋の沖縄キャンプでのことだった。夕暮れ前のサブグラウンドに現れた落合は、異様に細長いノックバットを手にしていた。ジャンパーを羽織ったまま、荒木に向かって緩やかなゴロを打ち始めた。身構えていた荒木が思わず拍子抜けするくらいに何の変哲もない打球だった。ノックは強度を上げて行くわけでもなく、平凡なゴロが淡々と続いた。
だが十分、二十分と経過するにつれ、荒木はあることに気づいた。
この打球は生きている……。
黒土をわずかに削り、静かに這ってくる白球は、荒木の息遣いの乱れや足の疲れをわかっているかのようだった。常にグラブがようやく追いつく場所へ、ギリギリの速さで飛んできた。まるでボールがノックの受け手をじっと観察しているかのようだった。
(中略)
もうそろそろだろう……。
プロで十年近く生きていると、さじ加減が分かってくる。(中略)ノックを打つ側にも受ける側にも、ある程度のパフォーマンスや予定調和が存在する。だから、そろそろ終わりだと感じた頃合いで選手はダイビングするのだ。追いつけない打球に飛び込む姿が、ユニホームについた泥が、鬼の看板を背負った監督やコーチを満足させる。観衆を納得させる。それで終わりだ。
荒木はもう一度、チラリと時計を見ると、落合の打球に飛び込んだ。
すると、それまで無言でノックを打っていた落合が鋭く言った。
「飛び込むな!」
荒木は一瞬、呆気にとられた。
「飛び込んだら意味がない」
新しい指揮官はそう言うと、また淡々とバットをふるい始めた。
(中略)落合のノックには、予定調和がまるで存在していなかった。
暮れなずむグラウンドで、ジャンパーを着たままの落合が、立ち尽くす荒木の方へゆっくりと歩いてきた。そして言った。
「野球っていうのはな、打つだけじゃねえんだ。お前くらい足が動く奴は、この世界にそうはいねえよ」
痺(しび)れるような感覚が体を巡った。プロに入って初めて等身大の自分を認められたような気がした。
(中略)
つまり、ほとんどの勲章は落合が現れてから手にしたものだった。
だから二〇一〇年に突然、働き場をショートに移され、すべてを失っていくような地獄に落とされても、荒木は落合の言葉の意味を考え続けることができた。
「さじ加減」「予定調和」。一般社会は、そのようなことに満ちている。プロスポーツの世界も例外ではない。プレーの厳格さよりもその場の雰囲気を優先するようなことが、この世界にもあることを知ったのは、私がプロ野球担当記者になって間もないころだった。